
健康商品の販売は法律的にダメなの?法律は難しくてよくわからない
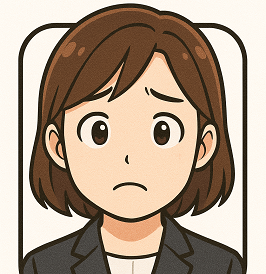
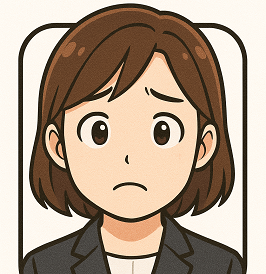
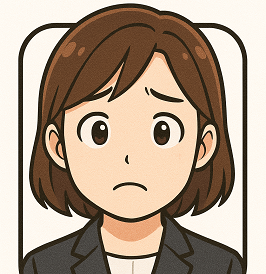
韓国コスメのクラウドファンディングを見つけたけど、販売しても大丈夫ですか?
クラウドファンディングで大きな成功を収めるプロジェクトを見てみると、ガジェットや家電といったジャンルの他に、革新的な健康グッズやコスメアイテムが支援金を集めていることも珍しくありません。
マッサージ器具、美顔器、ウェアラブルデバイス、オーガニック化粧品など、消費者の健康・美容意識の高まりとともに、これらのプロジェクトへの注目度は年々増しています。
しかし、ここで多くの起案者が見落としがちなことが、薬機法という重要な法律です。「製品開発も順調だし、プロジェクトページもできた!」と思っていたら、実は法的な許可が必要だった…そんな事態に陥らないために、今回は薬機法の基本から実践的な対策まで、分かりやすく解説します。
薬機法とは?「知らなかった」では済まされない基本知識


クラウドファンディングで人気の健康ガジェットや化粧品を販売する場合、薬機法の取り扱いが重要になります。
ここでは薬機法の基本と、なぜクラウドファンディングで重要になるのかを解説します。基本事項を押さえることで、プロジェクトに潜むリスクを大幅に減らせます。
薬機法の目的と規制対象
薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の品質・有効性・安全性を確保し、国民の健康を守ることを目的とした法律です。
正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
薬機法により、品質・有効性・安全性が管理された医薬品や医療機器、化粧品が市場に出回ることで、私たちは安心してこれらの製品を使用できます。
また、薬機法を遵守していると表明することで、製品を市場に流通させる事業者の信頼性も確立されます。
医薬品:病気の治療や予防に使われる薬。
医薬部外品:治療とまではいかないものの、予防や衛生を目的とするもの。「薬用」とつく化粧品や育毛剤などがこれにあたります。
化粧品:体を清潔にしたり、美しく見せるためのもの。ファンデーション、シャンプー、一般的な基礎化粧品など。
医療機器:病気の診断・治療・予防に使われたり、身体の構造や機能に影響を与えたりする機械器具。マッサージ器や血圧計、美顔器の一部も含まれます。
再生医療等製品:細胞加工製品など。
クラウドファンディングにおける健康ガジェットや化粧品プロジェクトの人気の背景
近年、健康志向の高まりと美容への関心の深化により、クラウドファンディングでは健康・美容関連プロジェクトが多数おこなわれ、大きな人気を集めています。
健康系・美容系製品は、個人のQOL(生活の質)向上に直結するため、支援者の共感を得やすく、数百万の支援金を集めるプロジェクトも珍しくありません。なかには、1億円を超える支援を獲得した事例も存在します。
24時間毎日体の変化を記録し、AIで解析をおこなう「RingConn 第2世代」


整理の日でもナプキンいらず、次世代【 超吸収型生理ショーツ Bé-A《ベア》】


自宅で使える健康機器:マッサージ器、電気治療器、測定機器、機能性枕など
美容ガジェット:美顔器、LED治療器、超音波機器など
ウェアラブルデバイス:心拍計、血圧測定器、活動量計など
コスメ・スキンケア:オーガニック化粧品、機能性化粧品など
クラウドファンディングで人気の健康・美容アイテム、なぜ薬機法に注意が必要?
健康に良さそう、美容に効きそうな商品は注目を集める一方、薬機法の規制対象と隣接する分野です。
たとえば、海外でリラックスグッズとして販売されている製品でも、日本で「利用するだけで肩こり解消」と謳ってしまえば、それは医療機器と見なされる可能性があります。



クラウドファンディングは応援購入だから、通常の販売とは違うのでは?
と思うかもしれません。
しかし、法律上は不特定多数の支援者に製品を提供する時点で明確に販売行為と見なされます。そのため、プロジェクトの起案者は事業者として、薬機法を遵守する義務があるのです。
薬機法を無視した場合のリスク
薬機法に違反した場合、以下のような深刻なリスクが発生します。
- 法的処罰
-
- 業務停止命令
- 製品回収命令
- 刑事罰(懲役・罰金)
懲役や高額な罰金が科される可能性があります。
- 経済的損失
-
- 製品回収費用
- 損害賠償請求
- プロジェクト中止による機会損失
業務停止命令や、製品の回収命令が出されます。 回収には多大な費用と労力がかかります。
- 信用失墜
-
- 支援者からの信頼失墜
- メディアでの報道
- 今後のプロジェクト実施困難
支援者の信頼を裏切り、返金対応やSNSでの炎上につながります。
特にクラウドファンディングでは、支援者との信頼関係が事業の根幹をなすため、法的トラブルによる信用失墜は、単なる罰金以上の深刻な影響をもたらします。
商品別に見る!必要な許認可・手続きチェックリスト
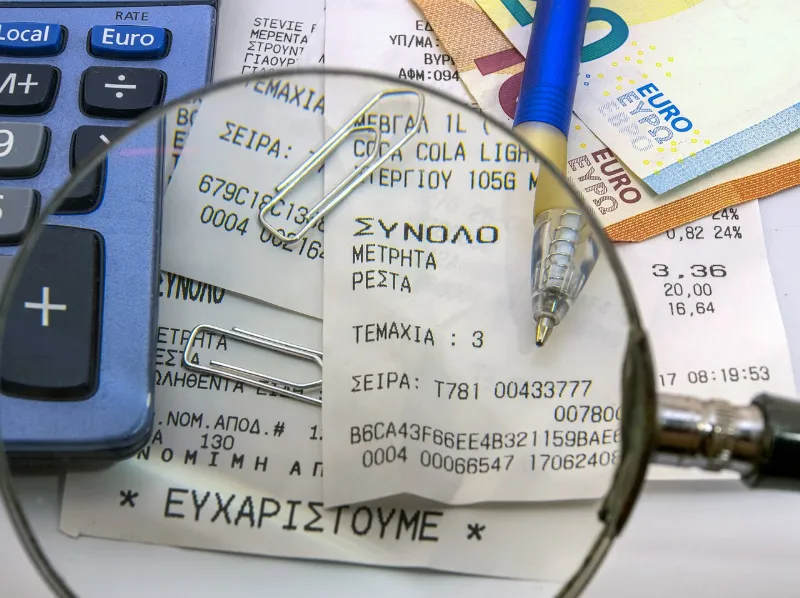
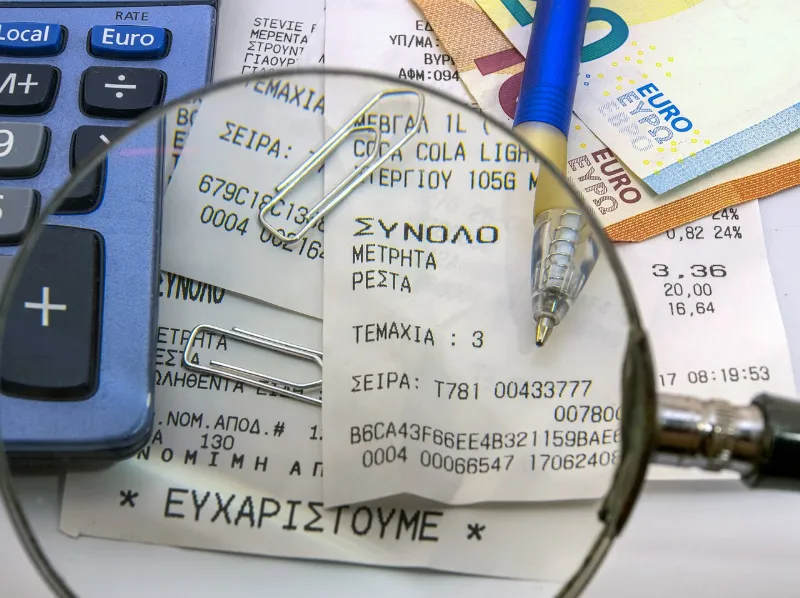
取り扱う商品がどのカテゴリーに分類されるかで、薬機法遵守に必要な許可や手続きは大き
く変わります。ここでは、クラウドファンディングで特に多い3つのジャンルについて解説します。
ヘルスケア・健康機器ガジェット
マッサージ器、美顔器、健康状態をモニタリングするウェアラブルデバイスなど、人の身体の構造や機能に影響を与える製品は基本的に医療機器に該当すると判断してください。
医療機器には人体へのリスクに応じて、クラスI~IVまで4つのクラスに分類されます。
| クラス | 例 |
| クラスI(一般医療機器) | 一部の電気歯ブラシ、X線フィルム |
| クラスII(管理医療機器) | 家庭用マッサージ器、血圧計、一部の美顔器 |
| クラスIII・IV(高度管理医療機器) | 人工呼吸器、ペースメーカー |
クラウドファンディングで扱うガジェットの多くはクラスⅡに該当することが多いですが、いずれにせよ専門的な手続きが必須となります。
化粧品・医薬部外品(コスメ類)
オリジナルブランドの化粧品や海外のユニークなコスメも人気ですが、薬機法の対象としてみなされます。
| 分類 | 例 |
| 化粧品 | ファンデーション、シャンプー、基礎化粧品 |
| 医薬部外品 | 薬用化粧品、育毛剤、制汗剤 |
必要な許可
化粧品を販売するには、主に2種類の許可が必要です。
化粧品製造販売業許可
自社ブランドの化粧品を市場に出荷・販売するために必須の許可です。 製品の品質や安全性について、すべての責任を負うのがこの製造販売業者です。
化粧品製造業許可
化粧品の製造行為(中身の製造、容器への充填、ラベル貼り、保管など)を行うための許可です。 特に注意したいのが、輸入品に日本語の成分表示ラベルを貼る作業も製造行為にあたるという点です。 自社の倉庫でラベルを貼るだけでも、この許可が必要になります。
一方、医療部外品(薬用化粧品など)を扱う場合は、医薬部外品製造販売業許可を取得するのが原則です。
医薬部外品製造販売業許可
医薬部外品製造販売業許可は、医薬部外品を自社名義で国内市場に出荷・流通させるために必要な都道府県知事の許可です。単なる販売や製造だけでなく、製造した製品の品質・安全性を保証する事業者として届け出・管理することが求められます。
サプリメント・健康食品
サプリメントや健康茶・機能性表示食品などは、基本的には食品として扱われ、薬機法ではなく食品衛生法・健康増進法の管轄となります。 そのため、薬機法上の許可は原則不要です。
食品衛生法については、こちらの記事で解説しています。
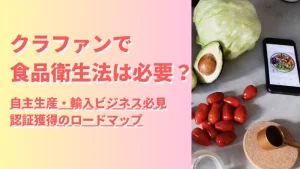
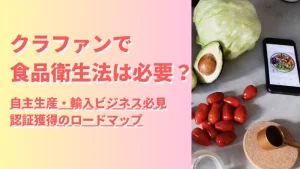
しかし、以下の点には注意が必要です。
成分
海外のサプリに含まれる成分が、日本では医薬品成分と見なされる場合があります。この場合、無許可での販売は違法となります。
広告表現
「飲むだけで病気が治る」「痩せる」といった、医薬品のような効果をうたうことは、薬機法で固く禁じられています。たとえ中身がただのお茶でも、表現次第で薬機法違反になるのです。
食品だから大丈夫とは考えず、成分と広告表現には細心の注意を払いましょう。
雑貨との境界線
製品が医療機器、医薬部外品、化粧品のいずれにも該当しない場合、一般的に雑貨として扱われます。しかし、この境界線は非常に曖昧で、誤解が生じやすいポイントです。
たとえ海外で雑貨として販売されていても、日本国内での定義や製品の使用目的、効能・効果の表現によっては、医療機器や化粧品と見なされる可能性があります。
広告文や商品の紹介ページを作成する際は、薬機法のNGワードに抵触しないことを重視してください。
詳しくは「雑貨として販売する際の注意点」にて解説します。
認証を取得するための具体的な流れと必要書類


ここでは、医療機器と化粧品を例に、実際に認証を取得し、販売を開始するまでの流れを具体的に解説します。
必要な要件と準備
日本国内で医療機器、医薬部外品、化粧品を販売するためには、製造販売業許可の取得が必須です。製造販売業許可は、製品の品質管理や安全管理に最終的な責任を負う者(製造販売業者)に与えられる許可のことであり、許可を所有しないまま製品を市場に流通させることはできません。
製造販売業許可の取得には、以下の専門的な要件を満たす必要があります。
- 総括製造販売責任者の設置
-
薬機法に関する専門知識と実務経験を持つ責任者の配置が義務付けられています。
- 品質保証責任者の設置
-
製品の品質管理体制を統括し、製品の品質が一定の基準を満たしていることを保証する責任者が必要です。
- 安全管理責任者の設置
-
市販後の製品の安全性に関する情報収集、評価、対応(副作用報告など)を統括する責任者が必要です。
- GQP(Good Quality Practice)省令適合
-
製造から出荷までの品質管理に関する基準を満たす必要があります。これは、品質管理システムの構築、手順書の作成、文書管理など、広範な準備を伴います。
- GVP(Good Vigilance Practice)省令適合
-
市販後の安全管理に関する基準を満たす必要があります。これには、製品の安全性情報の収集、評価、措置、行政への報告などが含まれます。
製造販売業許可の取得とは別途、個々の製品についても各種認証取得が必要となります。
医療機器として認証を取得するまでの手順
まずは自社製品が医療機器に該当するか、どのクラスに分類されるかを正確に判断します。 この段階で自己判断せず、必ず行政書士や薬事専門のコンサルタントに相談しましょう。
責任者の設置や管理体制を整え、都道府県に医療機器製造販売業許可を申請します。
製品の安全性や有効性を示す各種資料を準備し、第三者機関(クラスⅡの場合)やPMDA(クラスⅢ・Ⅳの場合)に申請します。
承認(承認申請)
クラスIII・IVの高度管理医療機器に必要です。PMDA(医薬品医療機器総合機構)による厳格な審査を受け、厚生労働大臣の承認を得る必要があります。これは最も厳しく、時間も費用もかかる手続きです。
認証(認証申請)
クラスIIの管理医療機器に必要です。PMDAに登録された第三者認証機関による認証を受けます。承認に比べて審査は簡略化されますが、製品の安全性と有効性を示すデータが必要です。
届出(届出提出)
クラスIの一般医療機器に必要です。PMDAに届出を提出するだけで、原則として審査は不要です。ただし、製造販売業許可の要件であるGQP/GVP体制の整備は必須です。
製造販売業者には品質管理・製造管理の徹底が求められるため、ISO13485等に沿った社内手順の整備や担当者教育を行います。申請プロセスの中でQMS適合性調査(書面審査や実地調査)が実施され、ここをクリアして初めて製品認証が完了します。
認証を取得した製品には、所定の範囲で医療機器マークや認証番号の表示、添付文書の用意などが必要です。また副作用や不具合発生時の報告体制も構築しておきます。
これらを怠らず準備した上で、ようやく正式に販売(リターン提供)開始となります。
化粧品として販売するまでの手順
製品のコンセプトを固め、成分や製造方法を検討します。すでに海外で完成品がある場合は、その全成分リストを入手してください。
入手した各種資料は、行政書士や薬事専門のコンサルタントに共有・相談し、日本で認証を受けられるかどうか、事前に確認しましょう。
自社を販売元とするなら、化粧品製造販売業許可の申請を行います。必要に応じて自社または委託先で化粧品製造業許可も取得します。
海外製品を扱う場合は、海外メーカーと連絡をとり、化粧品外国製造販売業者届出書をPMDAに提出してください。
オリジナル処方の場合は、試作品を試用しながら安定性(温度変化で分離しないか等)やパッチテストによる皮膚刺激の有無など、商品クオリティ確認を行います。
薬機法上必須ではありませんが、トラブルを未然に防ぐ品質検査として重要です。
また、輸入品の場合は現地で安全性試験済みか確認し、不安があれば日本で改めて検査機関に依頼することも検討しましょう。
輸入の場合は、輸入時に税関へ化粧品輸入の届出を行います。食品と異なり事前の検疫所届出はありませんが、税関で必要書類(製造販売業許可証や届出受理番号)が求められることがあります。
物流面では、保管先が化粧品製造業許可を持っているか(自社倉庫なら要許可、営業倉庫に委託ならその倉庫業者が許可を持っているか)も確認が必要です。
品ごとに化粧品製造販売届出を提出し、行政上の登録を完了させます。
輸入商品の場合、日本語表示ラベルを用意し、容器や外箱に貼付してください。
海外製品を輸入して販売する場合の重要ポイント
前述にも記載しておりますが、海外の魅力的な製品を輸入し、クラウドファンディングの製品として扱いたい場合は注意が必要です。
日本の法律が絶対
海外で承認・認証(例:アメリカのFDA、ヨーロッパのCEマーク)を受けていても、それらは日本では通用しません。 日本の薬機法に基づき、改めて許可や認証を取り直す必要があります。
「個人輸入」との違いを理解する
個人が自分で使用するために海外から製品を取り寄せる個人輸入は、一定の範囲で許可が不要です。 しかし、クラウドファンディングで不特定多数の支援者にリターンとして提供するのは、明確な事業としての販売(営業輸入)であり、薬機法上の許可が必須です。 この違いを混同しないようにしましょう。
責任の所在を明確に
輸入代行業者に依頼する場合でも、薬機法上の最終的な品質・安全管理の責任は、許可を持つ製造販売業者(つまり、あなたやあなたの指定した国内業者)にあります。 代行業者に任せれば責任を免れるわけではないことを肝に銘じてください。
成分表示の確認と日本語表記
とくに化粧品や健康食品を輸入する場合、製品成分が日本の規制に適合しているか、表示が日本の基準を満たしているかを詳細に確認する必要があります。
また、薬機法では国内販売する以上、表示や添付文書は日本語で適切に記載する義務があります。特に効能効果・使用方法・成分・副作用注意喚起など重要事項は、日本の基準に沿った文言で記載する必要があります。
クラファンのリターンとして発送する際にも、日本語の説明書や注意書きを同梱するようにしましょう。
税関での手続き
薬機法に係る商品を営業目的で輸入する際は、税関で輸入申告する際に必要な許可証や認証書の写し提出が求められます。
例えば医療機器なら製造販売業許可証や外国製造業者認定証、品目ごとの認証書など、化粧品なら製造販売業許可証と製造業許可証(該当する場合)などです。それらが揃っていないと輸入自体が認められません。
薬機法関連の認証取得にかかる費用と期間のリアル


薬機法関連の認証取得にかかる費用や取得までの期間は、クラウドファンディングのプロジェクト計画を立てるうえで欠かせない要素です。目標金額の設定やプロジェクトの開始時期にも大きく関わってきます。
ここでは、各種認証取得に必要な費用と期間の目安について、わかりやすく解説します。
認証取得にかかる費用
- 製造販売業許可取得
-
申請手数料:5万円~20万円
QMS調査費用:50万円~500万円
外部コンサルタント費用:100万円~500万円 - 製品別手続き・医療機器
-
クラスI医療機器届出:数万円
クラスII医療機器認証:50万円~300万円
クラスIII・IV医療機器承認:200万円~1,000万円以上 - 製品別手続き・化粧品
-
化粧品製造販売業許可:5万~9万円程度(地域による)
化粧品製造業許可(包装・表示・保管):数万円
医薬部外品承認:200万円~800万円 - その他の費用
-
試験費用:製品によって数十万円~数百万円
責任者の人件費:月額50万円~100万円
書類作成・翻訳費用:数十万円~
※これらはあくまで目安です。製品の複雑さや、専門家への依頼範囲によって大きく変動します。特に、コンサルタント費用などの見えないコストが予期せぬ負担になることもあるため、余裕を持った資金計画が重要です。
主な手続きに要する期間の目安
- 製造販売業許可取得
-
3~6ヶ月
許可申請と並行して、体制構築に時間がかかるため、早めの準備が必要です。
- 製品別手続き・医療機器
-
クラスI医療機器届出:1週間~1ヶ月
クラスII医療機器認証:3~6ヶ月
クラスIII・IV医療機器承認:6ヶ月~1年以上 - 製品別手続き・化粧品
-
化粧品製造販売業許可:1~2か月
化粧品製造販売届出:数日
医薬部外品承認:6ヶ月~1年以上
化粧品の安定性試験:1ヶ月~数ヶ月
プラットフォームの事前審査:1~2週間
これらの期間は、書類に不備がない場合の目安です。修正が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。
認証取得の手間と費用を賢く抑えるテクニック


薬機法に基づく手続きは複雑で費用もかかりますが、工夫次第でコストを抑えることが可能です。ここでは、実践的なコスト削減テクニックをご紹介します。
事前相談をフル活用:行政機関や専門家を味方につける
申請前に関係機関へ相談することで、要件や書類の書き方に関するアドバイスを受けられ、審査がスムーズに進みます。
都道府県の薬務課
許可申請の窓口である都道府県の薬務課では、無料で基本的な相談に応じてくれます。まずはこちらで大まかな方向性を確認するのがおすすめです。
PMDAの相談窓口
医療機器の承認申請を検討している場合は、PMDA(医薬品医療機器総合機構)の事前面談制度などの相談制度を活用できます。申請区分やデータ要件などを事前に確認できます。
薬事系コンサルタント・行政書士に相談
費用はかかりますが、薬事系コンサルタントや行政書士に早期相談することで、誤った手続きや時間のロスを防ぐことができます。
類似製品の認証情報を調査・活用する
既存の類似製品が取得している認証情報を調査することで、自社製品に求められる要件や申請区分のヒントを得られ、効率的に申請準備を進められます。PMDAのデータベースや、医療機器総合機構の承認情報検索を活用しましょう。
指定製造販売業者(DMAH)の活用
薬機法における「指定製造販売業者(DMAH:Designated Marketing Authorization Holder)」とは、外国製医療機器を日本で販売する際に、国内で製造販売業の許可を持つ業者を選任し、製造販売に関する業務を委託する制度です。
この制度を活用することで、自社で製造販売業の許可を取得せずに、認可済みの国内業者に製品の販売手続きを委託することが可能になります。医療機器の輸入販売を検討している企業にとって、初期費用と手続きの手間を抑える有効な方法です。
薬機法以外の関連法規制


クラウドファンディングで物販系の商品を取り扱う際には、薬機法だけでなく、他にも注意すべき法規制がいくつか存在します。
ここでは、商品ジャンルごとに関係する主な認証や関連法令についてわかりやすく紹介します。
無線機能搭載製品の技適マーク
Bluetooth、Wi-Fi、NFC等の無線通信機能を搭載した製品では、技適マーク(技術基準適合証明)が必要です。
- Bluetooth:ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ等
- Wi-Fi:IoTデバイス、ネットワークカメラ等
- NFC:決済機能付きデバイス等
PSE認証
電気用品安全法という法律に基づいて、電気製品が国の定めた安全基準に適合していることを証明する安全の証であり、ガジェットや家電製品を扱う際はPSE認証の対象であるかの確認が必要となります。
- モバイルバッテリー
- ACアダプター
- スマート家電
- USB給電・リチウムイオン蓄電池の製品
食品衛生法(キッチン用品)
コーヒーメーカーや調理器具など、食品に直接触れる製品を扱う場合は、食品衛生法の基準を満たす必要があります。
- スマート炊飯器
- フードプロセッサー
その他関連法令
- PL保険(生産物賠償責任保険)の検討
-
万が一、自社の製品が原因で消費者に損害(ケガや火災など)を与えてしまった場合に備え、PL保険への加入を推奨します。
- 知的財産権
-
あなたの製品のデザインやネーミングが、他社の特許権や商標権を侵害していないか、事前に確認することも忘れてはいけません。
雑貨として販売する際の注意点
薬機法の規制を避けるために、雑貨として販売することを検討する起案者も多くいますが、十分な注意が必要です。雑貨として販売できる製品の条件や、効果・効能に関する表現規制についての知識は欠かせません。
ここでは、雑貨として健康系・美容系の商品を売り出す際に注意すべきポイントを解説します。
雑貨として販売できる製品の条件
薬機法の規制を受けない雑貨として販売できるのは、その製品が医療機器、医薬部外品、化粧品のいずれの定義にも当てはまらない場合のみです。
雑貨の基本条件
医療機器の定義に該当しない
医薬部外品の定義に該当しない
化粧品の定義に該当しない
人体の構造や機能に影響を与えない
疾病の診断・治療・予防を目的としない
雑貨の具体例
単なる装飾品やアクセサリー
一般的な日用品
香りを楽しむだけのアロマグッズ
単純なリラクゼーション用品
「効果・効能」に関する表現規制の厳しさ
雑貨として販売する上で最も注意すべきなのが、広告表現で使う文言です。たとえ製品自体が雑貨であっても、広告で医療機器や化粧品のような「効果・効能」をうたうことは、薬機法で厳しく禁止されています。
雑貨では絶対NGな表現例
「肩こりが治る」「疲労回復」
「血行促進」「筋肉のコリをほぐす」
「肌が若返る」「シミが消える」
「抗菌」「ニキビ予防」
「飲むだけで痩せることができる」
これらの表現を使った時点で、その製品は雑貨ではなく、無承認の医療機器や無許可の化粧品と見なされ、薬機法違反に問われる可能性があります。
薬機法に抵触しないための表現ガイドライン
雑貨として販売する場合、下記項目を重点的にチェックしてください。
- NG表現は徹底的に避ける
-
前述のNG例のような、医療的な効果を連想させる言葉は一切使わないでください。
- 一般的な使用感や感覚的な表現に留める
-
「心地よい」「リラックスできる」「気分転換に」といった、個人の感想の範囲に留めましょう。
- 客観的な事実のみを記載する
-
製品の素材やデザイン、機能(例:「振動します」「温かくなります」)といった事実だけを伝え、それがもたらす「効果」には言及しないことが重要です。
使用可能な表現一例
心地よい
リラックスできる
気分転換に
おしゃれなデザイン
肌触りが良い
使用感が良い
認証取得の意義とメリット:なぜ薬機法対応は「投資」になるのか


- クラウドファンディングはテスト販売だから問題ないだろう
- 個人輸入の形式をとれば、許可は不要なはず
薬機法に対して、このような甘い見通しでプロジェクトを進めてしまうと、プロジェクトの頓挫はもちろん、企業の信用や将来のブランド価値にまで深刻なダメージを与えかねません。
ここでは、なぜクラウドファンディングでこそ薬機法への対応が重要なのか、その理由と長期的なビジネスに繋がるメリットについて解説します。
プラットフォーム審査の厳格化と法令遵守の重要性
誰でも手軽に挑戦できるイメージのあるクラウドファンディングですが、プラットフォーム側の審査は年々厳格化しています。特に、人の健康や身体に直接影響を与える健康器具・化粧品などは、薬機法や関連法規の遵守が厳しくチェックされます。
MakuakeやCAMPFIREといった主要プラットフォームでは、プロジェクトの申請時に以下のような薬機法関連の書類提出を求められることが珍しくありません。
提出する書類一例
製造販売業許可証の写し
製品の承認/認証/届出を証明する書類
製品の成分表や仕様書
これらの準備ができていなければ、審査を通過できず、プロジェクトを公開することすら叶わない可能性があります。つまり、薬機法対応は「後から考えればいい」ものではなく、クラウドファンディングのスタートラインに立つための最低条件なのです。
また、前述のPSE認証や食品衛生法関連の認証についても、薬機法と同様に認証を取得して書類提出が求められます。漏れ残しがないように注意してください。
支援者との信頼関係とブランド価値の構築
薬機法に基づく許可や認証は、その製品の「品質・有効性・安全性」が、国の定めた基準をクリアしていることの何よりの証明です。
これは、製品を選ぶ支援者にとって、「国のお墨付きがある、安心・安全な商品」という明確な評価軸となり、購入を後押しする大きな要因になります。特に、自分の身体に使う健康・美容関連製品であればなおさらです。
また、法律を誠実に遵守する姿勢は、事業者としてのコンプライアンス意識の高さを示し、支援者からの信頼に直結します。
たとえ今は小規模なプロジェクトであっても、この安心感という価値の積み重ねが、やがて強固なブランド価値を育て、将来のビジネスを支える大きな財産となるのです。
量産・一般販売へのスムーズな移行
多くの場合、クラウドファンディングは事業の第一歩に過ぎません。プロジェクトの成功後、ECサイトでの通常販売や、ドラッグストア・バラエティショップといった実店舗での一般販売を目指すのであれば、薬機法への対応は避けて通れない必須事項です。
クラウドファンディングの段階で適切な許可・認証を取得しておけば、その後の一般販売にあたって、製品の成分や仕様を大幅に変更したり、追加で高額な試験を行ったりする必要がなくなります。これにより、量産から販売までのフェーズへ極めてスムーズに移行することが可能になります。
また、BtoBでの卸販売や海外展開を視野に入れる際にも、「日本の厳格な法規制をクリアした製品である」という事実は、取引先に対する大きな信頼となり、ビジネスチャンスを広げる強力な武器となるでしょう。
結論
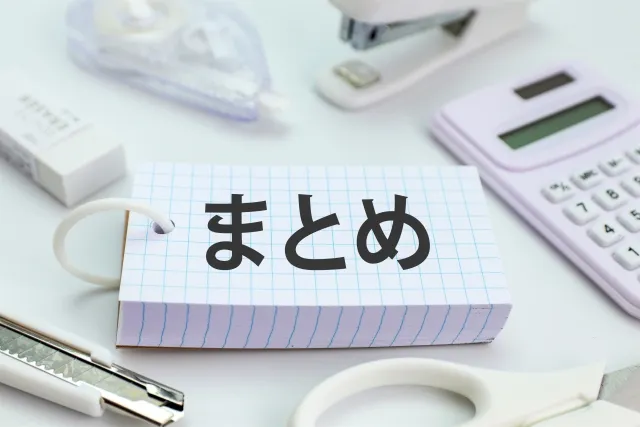
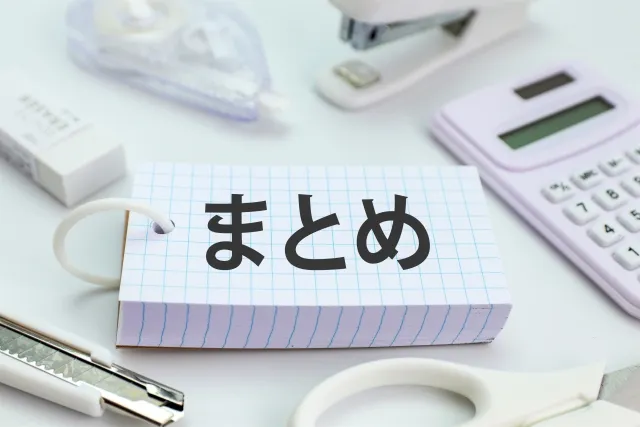
クラウドファンディングで健康・美容関連の製品を扱う際は、薬機法をはじめとする様々な法的規制への対応が不可欠です。薬機法は確かに複雑で、対応には時間と費用がかかります。しかし、適切に対応することで、消費者からの信頼を得ることができ、長期的に安定した事業を築くことができます。
- 早期の専門家相談:プロジェクト企画段階での法的確認
- 適切な製品分類:製品の法的位置づけの正確な把握
- 現実的な計画:必要な期間と費用の適切な見積もり
- 継続的な法的対応:販売開始後も続く法的義務の履行
とはいえ、これらの法的手続きをすべて自社だけで行うのは、現実的に非常に困難です。クラウドファンディングをおこなうこと自体も初めての方からすると、何から手をつければいいのか、誰に相談すればいいのか、不安に思うことも多いはずです。
「自分のプロジェクトはどの手続きが必要なのか?」と悩んでいる方、プロジェクトの成功に向けて専門的なアドバイスが必要な方は、ぜひLEAGUEにご相談ください。クラウドファンディングの企画から実施まで、無料でご相談に対応いたします。お気軽にご連絡ください。

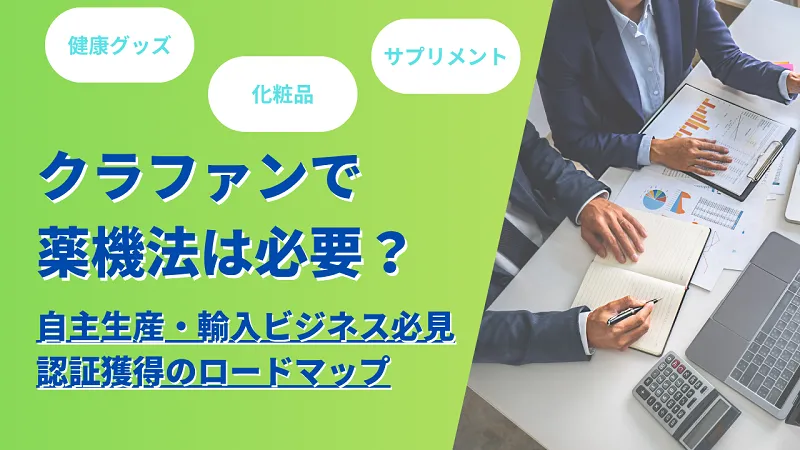
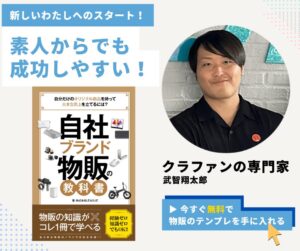
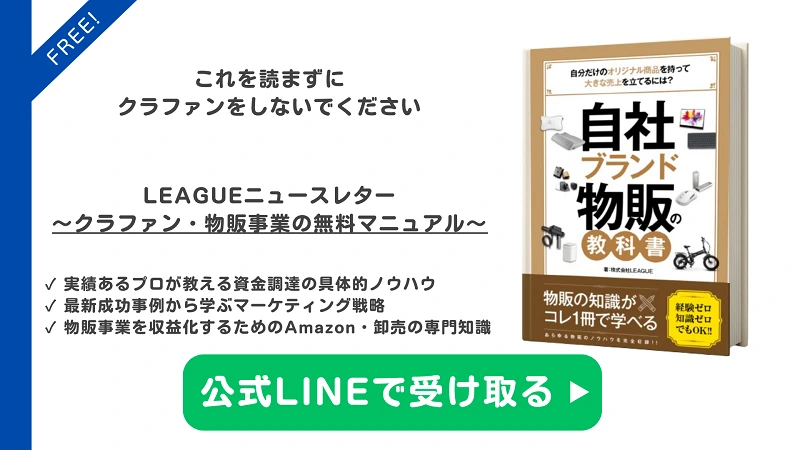


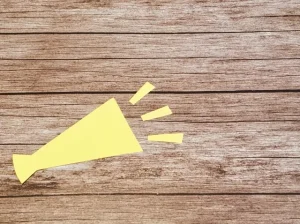
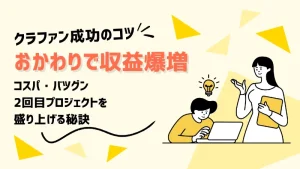






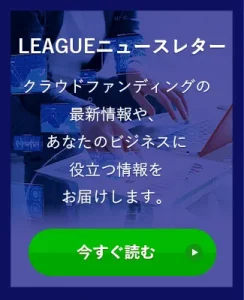
コメント