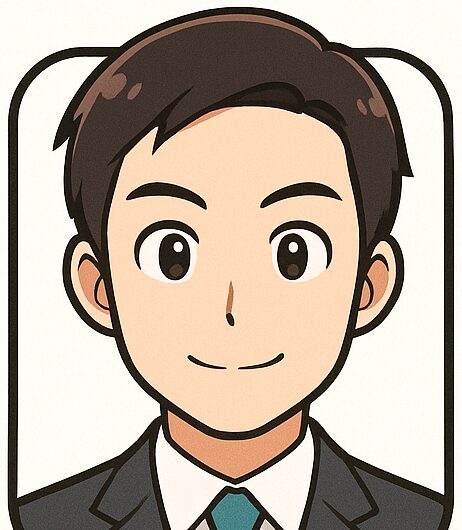
こだわりの手作りお菓子を、もっと多くの人に届けたい!
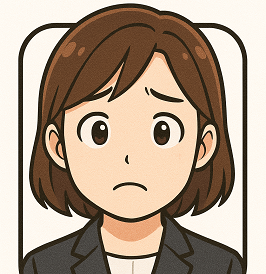
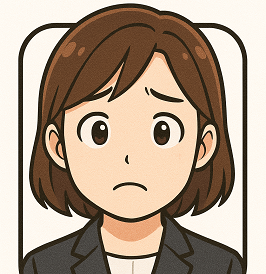
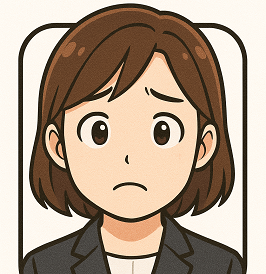
海外で見つけたおしゃれな食器、日本で販売しても本当に大丈夫?
クラウドファンディング(以下、クラファン)では、ユニークなガジェットや家電に加え、「食」や「器」のプロジェクトも高い人気を誇ります。作り手の想いが込められた食品や食器は多くの共感を集めやすい一方で、商品開発と同じくらい重要なのが法規制への対応です。
「これは良さそうだからクラファンで売ってみよう!」という情熱だけで突き進んでしまうと、思わぬ落とし穴にはまることも。その一つが食品衛生法という非常に重要な法律の存在です。クラファンはインターネットを通じた先行販売である以上、一般の流通と同様に法令遵守が求められます。
本記事では、一見難しそうに思える食品衛生法について、2025年7月時点の最新情報に基づきわかりやすく解説します。必要な手続き、費用や期間、そして賢く進めるためのコツまで網羅していますので、最後までお読みいただければ、あなたのプロジェクトを安全かつ成功に導くための知識がすべて身につくはずです。
動画で確認する
まずは動画でサクッと概要をつかんでから、詳細な解説へ進みたい方は、こちらの動画をぜひご覧ください。
食品衛生法とは?「知らなかった」では済まされない基本知識
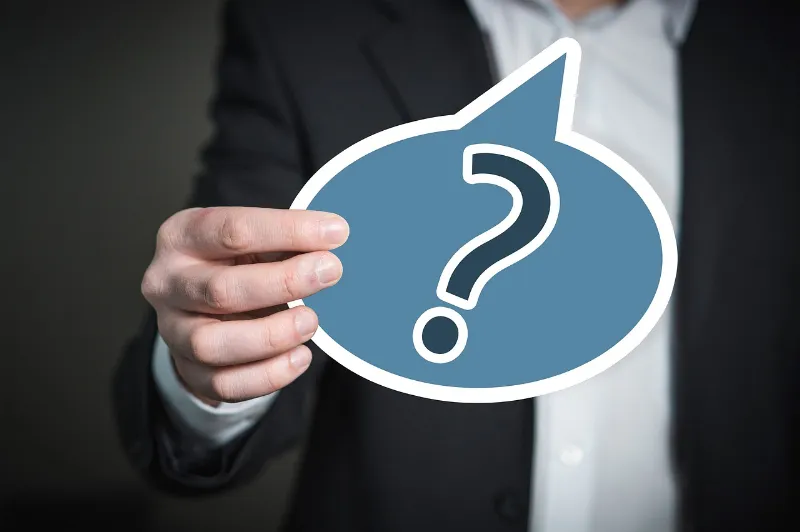
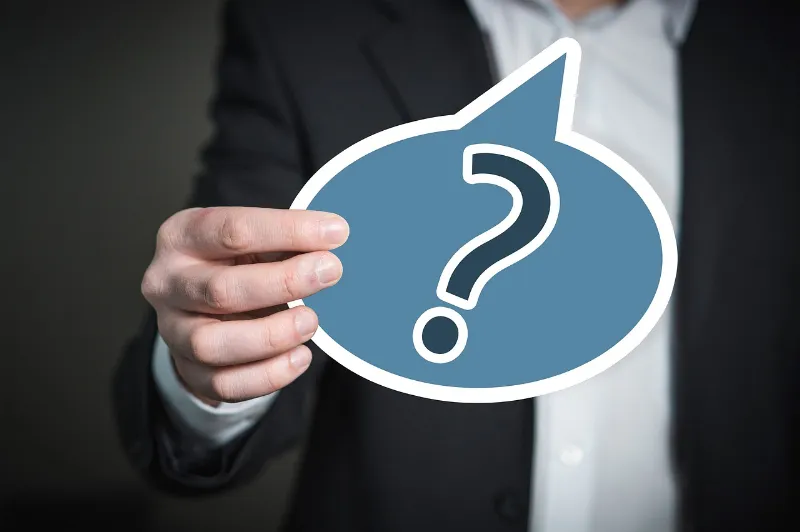
これからクラウドファンディングに取り組もうと考えている人の中には、食品衛生法について「なんとなく聞いたことはあるけれど、詳しくは知らない」という方も多いのではないでしょうか。しかし、この法律を理解せずにプロジェクトを進めてしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
まずは、食品衛生法の基本とクラウドファンディングとの関係について理解しましょう。
食品衛生法の目的と対象範囲をやさしく解説
食品衛生法をひと言で説明すると、「飲食による健康被害を防ぎ、国民の健康を守るための法律」です。食中毒や有害物質の摂取などから消費者を守るために国が定めた最低限のルールであり、食品を扱うすべての事業者にはこの法律を守る責任があります。クラファンで食品関連の商品を扱う場合も例外ではなく、必ず食品衛生法をクリアする必要があります。
では、具体的にどんなものが食品衛生法の規制対象になるのでしょうか?
「うちは食品そのものじゃないから大丈夫」と思っている方も注意が必要です。実は食品衛生法がカバーする範囲は非常に広く、口に入れるものや食品と直接触れるものが幅広く対象となります。


- 食品類
-
クッキーやケーキなどの菓子、調理済み食品、調味料、プロテインなどの健康食品、飲料など、口に入れるすべての飲食物が該当します(※医薬品・医薬部外品は除く)。
- 食器・調理器具・容器包装
-
カップ、お皿、お箸、スプーン、ストローはもちろん、鍋、フライパン、まな板、コーヒーメーカー、水筒といった食品に直接触れるあらゆる器具やその容器包装が対象です。
- 乳幼児用おもちゃ
-
おしゃぶり、歯固め、積み木、ブロックなど乳幼児が口に入れてしまう可能性のある玩具も対象に含まれます。
つまり、口に入れたり食品と接触するものであれば基本的に食品衛生法の規制対象と考えましょう。ただの雑貨だと思っていたものが実は対象だった…というケースも珍しくありません。
「知らなかった」では済まされないので、まずは自分のプロジェクト商品が法律上どのカテゴリーに当たるのか確認することが大切です。
クラファンで人気の飲食分野でもなぜ注意が必要?
クラウドファンディングでは、地域の特産品を使ったスイーツや新しい調理器具、オリジナル食品などが人気を集めています。




上記のプロジェクトのように、数百万や1千万を超える支援が集まることも珍しくはない食品系のクラファンですが、「クラファンは応援購入だから普通の販売とは違うのでは?」と思うかもしれません。
実際には、法律上は明確に販売と見なされます。プロジェクト起案者は食品等事業者として、食品衛生法や関連法規をすべて遵守する義務があります。
各クラファン・プラットフォームもこの点を重視しており、例えば大手のCAMPFIREでは規約で「食品衛生法・食品表示法上の義務に反する態様での食品の取扱い」を禁止しています。万一、必要な許可なく食品等を販売した場合、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」という非常に重い罰則(食品衛生法第52条)に処される可能性があります。
さらに、プロジェクトの強制中止、支援者からの信頼失墜、SNSでの炎上など、事業の存続を揺るがす事態にも発展しかねません。
以上のように、クラファンでの食品・食器プロジェクト成功の陰には法令遵守という土台が不可欠です。それでは具体的に、どのような手続きや許可が必要になるのか、次章から商品カテゴリ別に詳しく見ていきましょう。
商品別に見る!必要な許認可・手続きチェックリスト


食品衛生法の要求事項は、扱う商品によって異なります。ここではクラファンで特に多い商品カテゴリ別に、必要となる主な許認可・手続きを解説します。あなたのプロジェクトに該当するものをチェックしてみてください。
食品(加工食品・菓子・飲料など)を扱う場合
自ら食品を調理・製造してリターン品(支援者への送付商品)とする場合、その製造・販売を行う場所や施設に関して以下の対応が必須です。
提供する食品の種類に応じて、営業許可を管轄の保健所から取得するか、または営業届出を行う必要があります。営業許可が必要なのは、公衆衛生上リスクが高いとされる32種類の業種です(※2021年6月の法改正で従来の34業種から32業種に再編されました)。
| 区分 | 業種例 | クラウドファンディングでの関連例 |
| 営業許可が必要(32業種) | 飲食店営業、喫茶店営業 | 飲食店のリターン提供、カフェ開業 |
| 菓子製造業、パン製造業 | 手作り菓子、パンのリターン | |
| そうざい製造業 | 惣菜、弁当、ミールキットのリターン | |
| 食肉製品製造業、水産製品製造業 | ハム、ソーセージ、練り製品のリターン | |
| 冷凍食品製造業、漬物製造業 | 自家製冷凍食品、漬物のリターン | |
| 密封包装食品製造業 | 瓶詰、缶詰食品のリターン | |
| 営業届出が必要(許可業種以外) | 乳類販売業、氷雪販売業 | 牛乳、氷の販売(容器包装されたもの) |
| 食肉販売業(容器包装に入った食肉販売のみ) | パック詰めされた肉のリターン | |
| 魚介類販売業(容器包装に入った魚介類販売のみ) | パック詰めされた魚介類のリターン | |
| 食品の小分け業 | 大袋の食品を小分けして販売するリターン | |
| 届出不要業態 | 食品・添加物の輸入業、貯蔵・運搬業 | 海外からの食品輸入、倉庫保管、運送のみ |
| 常温長期販売品の販売業 | 特定の加工食品(例:はちみつ、食酢)の販売 | |
| 器具容器包装の輸入業、販売業 | 食器の輸入・販売 | |
| 農業及び水産業における食品の採取業 | 農産物・水産物の生産・収穫のみ |
該当業種を営むには保健所への申請と、業種ごとに定められた施設基準を満たすことが求められます。許可を取得した施設には、交付された営業許可証を見やすい場所に掲示する義務もあります。詳しくは厚生労働省や自治体の公表資料で確認できます。
例えば、容器包装された飲食料品を仕入れて販売するだけであれば、許可ではなく届出で営業可能なケースが多くなっています。実際、2021年の改正ではリスクが比較的低いと判断された業態(例:牛乳販売業、氷雪販売業、容器入りの精肉・鮮魚販売業など)は許可不要となり届出制に移行しました。
ただしプロジェクトの内容によって判断が分かれる場合もありますので、事前に所轄保健所に相談しましょう。
食品衛生責任者の配置
食品を扱う営業許可施設ごとに、必ず食品衛生責任者を1名以上置かなければなりません。
食品衛生責任者とは、日常の衛生管理を統括し食中毒等の防止に責任を負う役割です。経営者や店長である必要はありませんが、その施設に常駐するスタッフから選任しなければなりません。
この資格は、各都道府県などが実施する食品衛生責任者養成講習会を受講することで取得できます。講習は通常1日(6時間程度)で、衛生法規・公衆衛生・食品衛生などについて学び、修了時に資格証明書が交付されます。講習の受講料は約1万円前後が目安です。
なお、調理師・栄養士・製菓衛生師など関連資格を既に持っている人は、この講習会受講が免除され、そのまま食品衛生責任者として選任できます。スタッフに該当者がいれば有効活用しましょう。
もし開業時点で資格者を確保できなくても、食品衛生責任者設置誓約書を提出すれば数ヶ月の猶予を与えられる自治体もあります。いずれにせよ食品衛生責任者不在の営業は認められないので、必ず事前に手配してください。
衛生管理の制度化(HACCPの導入)
2021年6月の法改正により、原則すべての食品等事業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が義務付けられました。HACCPとは国際的に認められた衛生管理手法で、食品の製造・加工プロセス上の危害要因を分析し、どの工程でリスクを低減・管理するか計画・記録する仕組みです。従来の抜き取り検査とは異なり、工程ごとにモニタリングと記録を行うことで問題のある製品の出荷を未然に防ぎ、万一問題発生時も原因追及が容易になります。
HACCPの義務化と聞くと「うちのような小規模でも必要なの?」と思うかもしれませんが、基本的には全ての食品事業者が対象です。もっとも、小規模事業者等については厚生労働省が公表する業種別の手引書に沿って、簡略化したアプローチ(いわゆる「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」)で対応することが認められています。
これは難しい計画書をゼロから自作するのではなく、業界団体が作成したひな形(手引書)に従って衛生管理を実践する方法です。小規模な飲食店や個人事業者はこちらを参考にすれば、特別な知識がなくても取り組めます。
農林水産業の一次生産(農場での収穫・漁業の水揚げ等)はHACCP制度化の対象外ですが、それ以外では食品の輸入業、倉庫業(冷蔵・冷凍倉庫を除く)や、常温で長期保存可能な包装食品の販売業、器具・容器包装の輸入販売業など公衆衛生上のリスクが特に低い営業のみがHACCP適用除外とされています。
例えば常温保存できる包装済み食品の単なる小売や食器・容器の販売のみを行う場合は、一般的な衛生管理さえ実施すればHACCPによる管理までは求められません。
ただしこれらに該当するかどうか判断が迷う場合もありますので、必要に応じて所轄保健所に確認しましょう。
HACCPの制度化は努力義務ではなく法律上の義務です。そのため、正当な理由なく必要な衛生管理に取り組まないと食品衛生法違反となり得ます。
ただし、すぐに刑事罰が科されるわけではありません。通常は「保健所の立入検査→指導→改善命令」と段階を踏み、従わない悪質な場合に初めて「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」(法人は1億円以下の罰金)という罰則が適用されます。
食器・キッチン用品・容器包装を扱う場合
お皿やカトラリー、調理器具など食品に直接触れる製品をクラファンで提供する場合、食品そのものとは違い営業許可は不要です。食品衛生法上、これらの器具や容器包装の製造・販売業自体には飲食店のような営業許可制度はありません。
しかし製品そのものの安全性について、食品と同様に法律の規制を受けています。具体的には、その製品を専門の検査機関(化学物質評価研究機構・CERIや日本食品分析センター・JFCR)に提出し、材質から有害物質が溶け出さないかなどの試験を受けて、安全基準を満たしているという証明が必要があります
例えば陶磁器製の食器であれば鉛やカドミウムの溶出試験、プラスチック製品ならホルムアルデヒドの溶出試験など、材質ごとに定められた検査項目があります。一つの製品に複数の材質(例:プラスチックと金属)が使われている場合、それぞれについて試験が必要です。
検査に合格すると、その製品が日本の安全基準を満たしていることを示す試験成績書や食品衛生法適合証明書が発行されます。クラファンのプラットフォームによっては、プロジェクト審査時にこうした証明書の提出を求められる場合もあります。支援者に安全・安心を示す意味でも、製品テストは避けずにきちんと実施しましょう。
海外製の食器やキッチン用品を輸入して販売する場合、日本国内で流通させる前にその製品が日本の基準に適合していることを確認する責任は輸入者にあります。
海外メーカーのカタログに「FDA(米国食品医薬品局)承認」などと書かれていても、日本の基準とは異なるため日本向けの試験を改めて実施する必要があります。逆に海外メーカーが日本の食品衛生法試験に合格した証明書を持っている場合は、それを活用できることもあります。
個別ケースによって異なるため、専門機関や輸入代行業者に相談すると良いでしょう。
具体的な流れと必要書類


それぞれの手続は複雑に思えるかもしれませんが、段階を踏んで進めれば確実にクリアできます。ここでは実際の申請から認証取得までの流れを解説します。
食品の場合(営業許可)
食品衛生責任者がいない場合は、1名以上が講習会を受講し、食品衛生責任者としての資格を取得してください。
製品を製造する施設の図面などを持参し、どのような設備が必要か、基準を満たしているかを保健所に相談します。
保健所のアドバイスに基づき、シンクや手洗い場、冷蔵庫などを基準通りに整備します。
必要書類を揃えて保健所に申請します。
必要書類一例
飲食店営業許可申請書
食品衛生責任者設置届
施設の構造・設備平面図
営業設備の大要書
登記事項証明書
身分証明書など
保健所の担当者が実際に施設を訪れ、基準を満たしているかチェックします。営業者または責任者の立ち会いが必須です。
検査に合格すれば、晴れて許可証が交付され、営業を開始できます 。
食品の場合(営業届出)
必要書類を準備し、窓口または電子申請を行います。
営業届出書
食品衛生責任者設置届
施設の構造・設備図面
登記事項証明書など
申請方法
窓口提出:管轄保健所の生活衛生監視事務所へ直接提出する。
電子申請:厚生労働省「食品衛生申請等システム」からオンラインで提出する。
多くは届出内容の確認で手続きが完了します。製造・集団給食等は保健所による現地調査を行い、衛生管理体制を確認されます。
届出後、保健所から受理通知等が発行され、営業開始が可能となります。
食器・調理器具の場合(製品検査)
製品の材質や用途を伝え、どのような検査が必要か、費用はいくらかなどを確認します。
事前相談の用意書類
商品写真の入ったカタログ
原材料・成分または製造工程等に関する説明書
正式に申し込み、製品サンプル(検体)を検査機関に送付します。
検査機関で数日~数週間かけて試験が行われます。検査では以下の項目などが確認されます。
有害物質の含有量チェック
添加物の使用基準適合性
製造基準への適合性
検査に合格すると、証明書が発行されます。これを大切に保管し、必要に応じてプラットフォームに提出します。
海外製品を輸入して販売する場合の重要ポイント
クラファンの商品を海外から取り寄せて提供するケースでは、輸入時の手続きもクリアしなければなりません。食品衛生法では、販売目的で食品や器具等を輸入する際に守るべきルールが定められています。
検疫所への輸入届出
販売目的で食品や食器などを国外から輸入する場合、輸入の都度、厚生労働省の検疫所に対して食品等輸入届出書を提出する義務があります。これは輸入食品等の安全を確保するための事前届出制度で、税関で輸入通関する前に行わなければなりません。
届出書にはその食品等の原材料・成分や製造工程に関する説明書、輸出国の衛生証明書(必要に応じて)、過去に受けた検査の成績書(必要に応じて)などを添付します。
検疫所は提出書類に基づいて審査を行い、必要と判断すれば貨物の一部について検査(モニタリング検査や命令検査)を実施します。審査や検査の結果、その製品が食品衛生法の規格基準に適合し安全と確認されれば食品等輸入届出済証が発行されます。
食品等輸入届出済証は税関での輸入申告時に必要な書類で、この証がなければ販売用食品等は国内に持ち込めません。 万一審査の結果不適格と判断された場合、その商品は廃棄や積み戻し(送り返し)などの措置が取られます。
例えば検査で基準超過の農薬や重金属が検出された場合などは通関できず、輸入者の負担で返品・処分となります。こうしたリスクを避けるためにも、輸入前にきちんと試験を行い問題がないことを確認しておくことが重要です。
食品衛生法関連でかかる費用と期間のリアル


食品衛生法関連の許認可や製品検査には、費用や時間がかかります。これら負担はクラファンのプロジェクト計画(目標金額やスケジュール)にも大きく関わるポイントです。ここでは主な項目について、2025年時点での目安を紹介します。
主な手続き・検査にかかる費用の目安
- 営業許可申請手数料
-
業種や自治体によりますが1万円~2万円程度です。例えば東京都では飲食店営業許可が16,000円前後、菓子製造業許可が13,000円程度となっています。この他、施設改装が必要な場合はその費用も考慮します。
- 営業届出
-
届出自体に手数料はかかりません。
- 食品衛生責任者講習料
-
約1万円(テキスト代込み)程度が一般的です。地域によって若干異なります。
- HACCP対応費用
-
自社スタッフのみ(小規模事業者に限る)で体制整備する場合は主に労務コストのみです。
コンサルタントに依頼すると小規模事業者で5~10万円、規模が大きい場合50~100万円ほどの支援料がかかることもあります。
なお、HACCPそのものは認証を取得しなくても法律遵守できますが、任意で認証取得を目指す場合はさらに年間数十万円の維持費用が発生します。
- 製品の検査費用
-
材質や検査項目数によって数万円~数十万円と幅があります。簡単な材質検査なら1件あたり3万円程度から可能ですが、複数素材・多項目になると合計10万~50万円以上になるケースもあります。
目安として、陶器の鉛・カドミウム溶出試験で数万円、食品の成分分析で5万~20万円、乳幼児用おもちゃの安全性試験で5万~15万円程度です。
主な手続きに要する期間の目安
- 営業許可取得期間
-
施設の準備状況にもよりますが、保健所への相談開始から許可証交付まで概ね2~3週間は見ておきましょう。施設の改装や設備調達に時間がかかれば数ヶ月単位になることもあります。
- 営業届出の処理期間
-
オンラインまたは窓口で届出を行えば、内容確認後すぐに受理通知が発行され即営業開始可能です。現地確認が必要な場合でも通常数日~1週間程度で完了します。
- 食品衛生責任者資格の取得期間
-
講習会の日程次第ですが、早ければ1日で取得可能です。人気の講習は予約待ちになることもあるので、早めの申し込みを心がけましょう。
- 製品検査の期間
-
検体を提出してから証明書発行まで2~3週間程度が一般的です。混雑状況によってはさらに時間を要する場合もあるため、クラファン開始に間に合うよう逆算して依頼しましょう。
- 輸入手続き期間
-
前述の通り、検査なしでスムーズに通関すれば数日ですが、検査が入ると数週間~1ヶ月以上かかる可能性があります。
認証取得の費用と手間を賢く抑えるテクニック


クラウドファンディングで食品や食器をリターンとするプロジェクトを成功させるためには、食品衛生法の遵守が不可欠です。これは単なる法的義務に留まらず、支援者との信頼関係を築き、プロジェクトの持続可能性を確保するための戦略的な要素となります。
事前相談の重要性:保健所・検疫所を味方につける
食品衛生法に関する規制は多岐にわたり、個別のプロジェクト内容によって適用される法律や必要な手続きが異なります。自己判断では見落としや誤解が生じるリスクが非常に高いため、専門機関への相談が不可欠です。
最も確実な方法は、プロジェクトの企画段階から管轄の保健所(食品の製造・加工・販売の場合)や、輸入食品・食器の場合は検疫所の食品監視課に事前相談を行うことです。この事前相談は、プロジェクトを安全かつ合法的に進める上で最も重要かつ確実なステップと言えます。
正確な情報が得られる
自身のプロジェクトに必要な許可・届出を正確に把握できるだけでなく、施設基準やHACCPに沿った衛生管理に関する具体的なアドバイスを得られます。また、輸入手続きの詳細な確認や、リスクを最小限に抑える方法についての助言も期待できます。
無駄な作業がなくなる
最初に正しい道筋を教えてもらえるので、無駄な時間や費用の削減、トラブルの未然防止に繋がります。
信頼関係が築ける
早い段階から相談しておくことで行政機関との良好な関係を構築することは、万が一の事態発生時にもスムーズな対応に繋がるでしょう。
事前相談は基本的に無料で、電話やメールでも対応してもらえることが多いので、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。
認証取得済みのOEMメーカーや輸入代行業者に委託する
自社で一から認証を取得するのではなく、すでに認証を取得している業者に製造や輸入を委託する方法もあります。
OEMメーカーの活用
食器を扱いたい場合、自社で施設を持たなくても、すでに営業許可を取得しているOEM(他社ブランドの製品を製造する)メーカーに製造を委託する方法があります。
この場合、あなたは製造許可を取得する必要がなくなり、大幅に手間とコストを削減できます。
輸入代行業者・コンサルタントの活用
海外製品の輸入手続きは非常に煩雑です。専門の輸入代行業者やコンサルタントに依頼すれば、書類作成から検疫所とのやり取り、検査の手配まで、すべてを任せることができます。
手数料はかかりますが、失敗のリスクや手間を考えれば、結果的に安くつくことも少なくありません。
食品衛生法だけじゃない!プロジェクトページ公開前に確認すべき関連法規
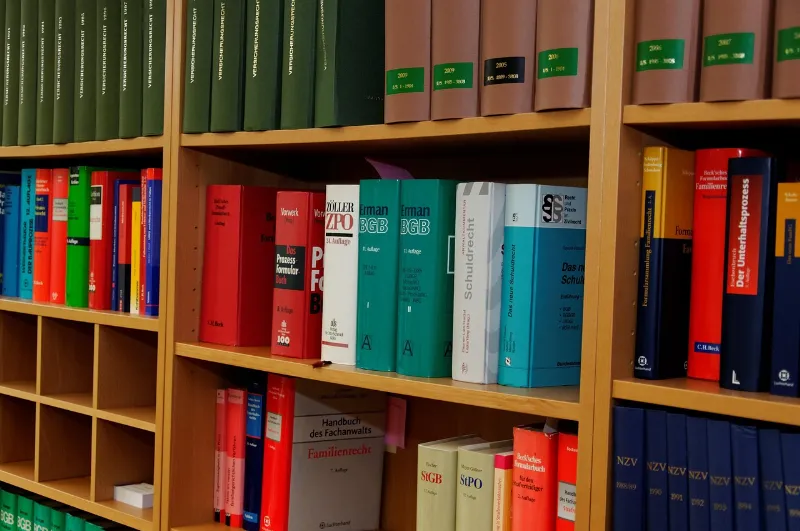
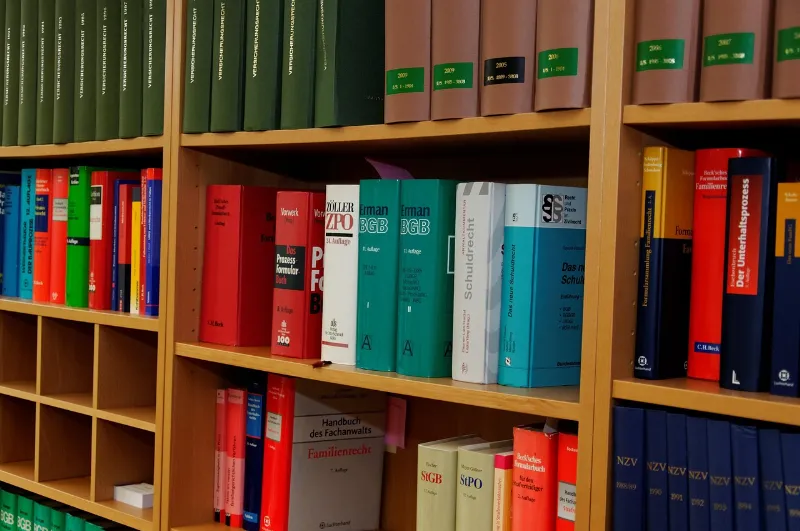
クラファンで食品関連商品を扱う際は、複数の法律が関わってくるため、総合的な法規制への対応が必要です。ここでは、食品関連プロジェクトで関係する、法令を紹介します。
誇大広告で炎上しないための景品表示法
景品表示法はウソや大げさな表現で消費者を騙すような広告を禁止する法律です。クラファンのプロジェクトページでは、商品の魅力を最大限にアピールしたいものですが、行き過ぎた表現は景品表示法に抵触する可能性があります。
ダメな例
「世界一おいしい!」「絶対に満足させます!」といった、客観的な根拠のない最上級の表現。
「飲むだけで痩せる!」といった、効果を保証するような表現。
このような誇張表現は、景品表示法に違反する可能性があります。支援者の期待を過剰に煽ることは、後のクレームや信頼失墜の原因にもなります。
「健康に良い」と謳う場合の薬機法
健康食品やサプリメント、ハーブティーなどをリターンとして扱う場合、特に注意が必要なのが薬機法(旧・薬事法)です。食品であるにもかかわらず、医薬品のような効果をうたうことは、厳しく禁止されています。
- 病気の治療効果を謳う表現
- 身体の構造や機能に影響を与えるという表現
- 医薬品的な効果効能の表示
NGな表記例
「このお茶を飲めば、不眠症が改善します」
「お茶を飲むことで、血圧が下がる」
OKな表記例
「リラックスタイムのお供に。やすらぐ香りのハーブティーです」
「美味しくて飲みやすい」
製品の魅力を伝えたいあまりに、いきすぎた表現方法とならない、法律の境界線を越えない表現を心がけましょう。
パッケージ表示に必須の食品表示法
リターンとして提供する食品には、食品表示法に基づいた正確なラベル表示が義務付けられています。これは、消費者が安全に商品を選べるようにするための、非常に重要なルールです。
- 名称
- 原材料名
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 製造者の氏名・所在地
- アレルギー表示(特定原材料8品目は必ず表示)
- 栄養成分表示
文字サイズや表示方法についても細かな規定があるため、事前に確認が必要です。手作りのジャムやクッキーなどの小さなパッケージであっても、これらの情報をすべて表示する必要があります。
その他関連法令
- PSEマーク
-
電気で動く調理器具(コーヒーメーカー、ミキサーなど)を扱う場合は、電気用品安全法に基づき、安全性を証明するPSEマークの表示が必須です。
- 知的財産権
-
あなたの製品のデザインやネーミングが、他社の特許権や商標権を侵害していないか、事前に確認することも忘れてはいけません。


テスト販売でも食品検査は必須!安全・安心なクラファン運営の第一歩
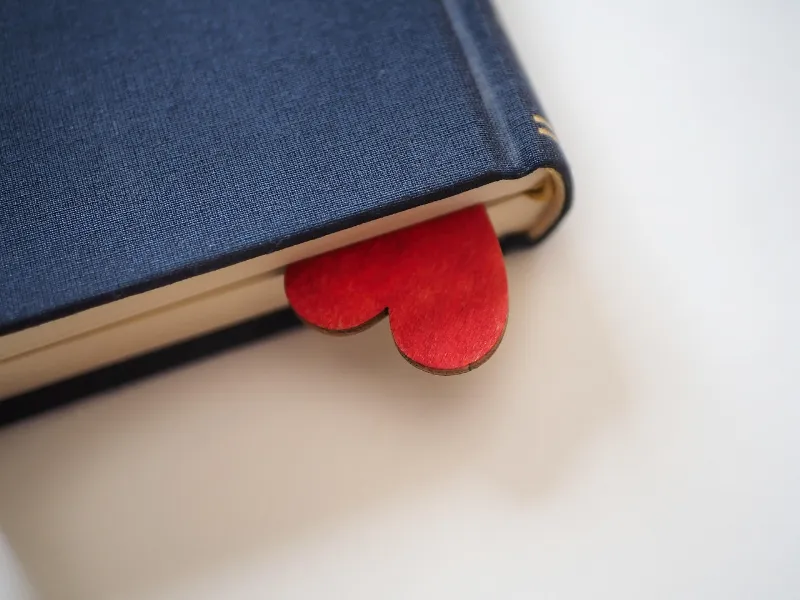
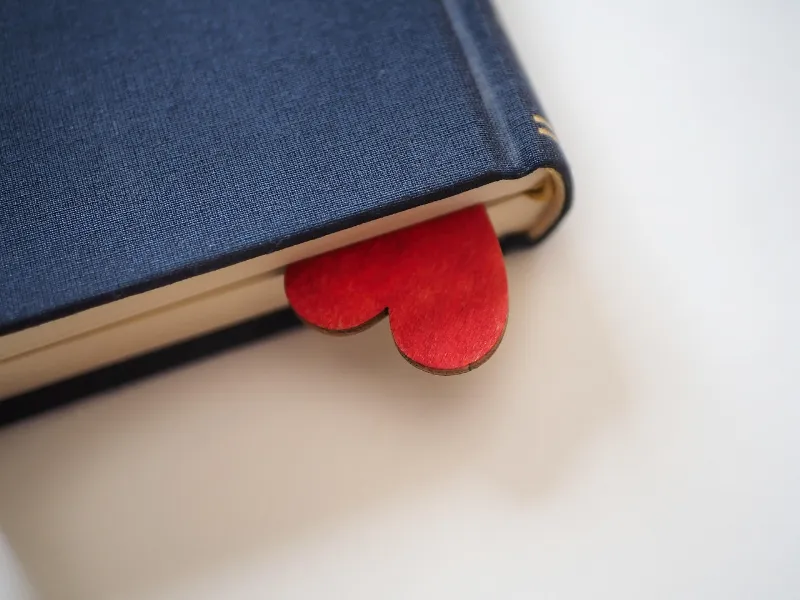
- 「個人の手作りだから問題ないだろう」
- 「クラウドファンディング期間中に許可を取れば大丈夫」
といった甘い見通しで、食品衛生法に基づく検査や許可取得を軽視してしまうと、食中毒などの重大事故やプロジェクトの頓挫はもちろん、築き上げたブランド価値を根底から揺るがしかねません。
ここでは、なぜクラウドファンディングで食品や食器を扱う上で、食品検査のクリアが重要なのか、その理由と長期的なメリットについて解説します。
プラットフォーム審査の厳格化と法令遵守の重要性
クラウドファンディングは誰でもプロジェクトを立ち上げやすい一方で、プラットフォーム側の審査は年々厳しくなっています。特に食品や食器のように直接人の口に触れる製品は、食品衛生法に基づいた営業許可や製品検査が必須です。
MakuakeやCAMPFIREといった主要なプラットフォームでは、プロジェクトの申請時に以下のような書類の提出を求められることも珍しくありません。
プロジェクト申請時に求められる可能性がある資料など
食品衛生法に基づく営業許可証
HACCPに沿った衛生管理を行っていることを示す書類
製品の安全性を示す試験成績書(食品衛生法適合証明書)
検査機関との契約書や見積書
こうした準備ができていなければ、そもそも審査を通過できず、プロジェクトを公開することすら叶わない可能性があります。つまり、食品衛生法への対応は「後でやればいいこと」ではなく、プロジェクトのスタートラインに立つための最低条件なのです。
支援者の信頼と安心感を得るために
クラウドファンディングでは、支援者は商品を買うだけでなく、想いを応援するという気持ちで支援してくれます。しかし、どれだけ想いに共感しても、衛生的に不安な商品にはお金を出しません。
食品検査をきちんと行うことは、以下のような支援者の不安を払拭します。
本当に口に入れても安全なのか?
日本の法律に適合しているのか?
表示されている成分や効能は正確なのか?
支援者にとっては、「許可・検査済み=安心して口にできる商品」という明確な評価軸となり、特にアレルギーを持つ方や、お子様のために商品を選ぶ方にとっては、購入を決定づける極めて重要な情報となります。
また、食の安全に関わる法律をきちんと守っているという姿勢は、作り手としての誠実さや品質管理に対する意識の高さを示す最高のPR材料になります。たとえ小さなプロジェクトであっても、こうした法令遵守の積み重ねが支援者からの信頼を育み、将来にわたってブランドの価値を高めていくのです。
量産・一般販売へのスムーズな移行
クラウドファンディングでの成功は、多くの場合、事業の第一歩に過ぎません。プロジェクト終了後に、スーパーや百貨店、ECサイトなどで一般販売を目指すのであれば、営業許可の取得や製品の安全性証明は避けて通れません。
先にクラウドファンディングの段階でこれらの法的な要件をクリアしておけば、リターン品の製造方法や仕様を大幅に変更することなく、そのまま量産・一般販売のフェーズへスムーズに移行できます。
さらに、飲食店への卸販売(BtoB)や、HACCP対応を武器に海外展開を視野に入れる場合においても、「国内の厳格な法規制をしっかりとクリアしている安全な製品である」という事実は、交渉を有利に進めるための大きな信頼性の証明となります。
結論


食品や食器を扱うクラファンは、ヒットの可能性が高い反面、法規制への対応が商品開発と同じくらい重要です。食品衛生法をはじめ関連法規は一見複雑に見えますが、一つ一つ段階的に取り組めば確実にクリアできます。
早めに動くこと
許可申請や検査には想像以上に時間がかかります。プロジェクト企画段階から法対応のスケジュールを組み込み、リターン発送の時期に余裕を持たせてください。
専門家を頼ること
自己判断は禁物です。わからないことは保健所や検疫所、食品検査機関、行政書士・コンサルタントなどプロの力を積極的に借りましょう。適切な助言により無用なミスや遅延を防げます。
各種検査には確実にコストと時間がかかります。しかし、これを必要投資として捉え、プロジェクト計画に適切に組み込むことで、安全で信頼性の高いクラウドファンディングを実行できます。
「自分のプロジェクトはどの手続きが必要なのか?」と悩んでいる方、プロジェクトの成功に向けて専門的なアドバイスが必要な方は、ぜひLEAGUEにご相談ください。クラウドファンディングの企画から実施まで、無料でご相談に対応いたします。お気軽にご連絡ください。

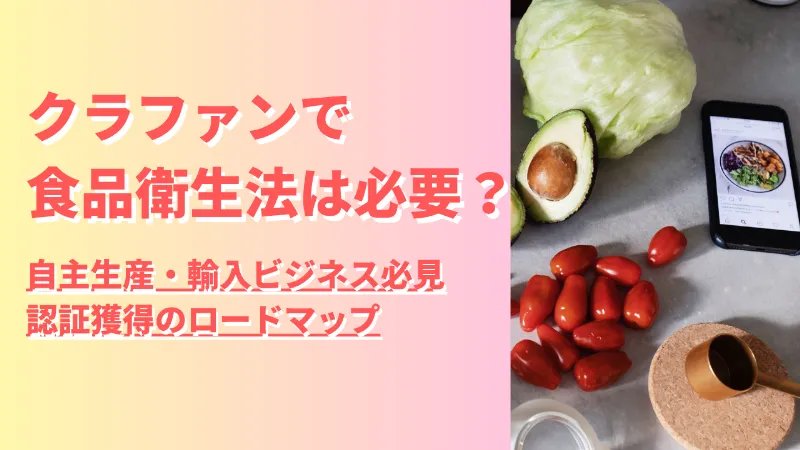
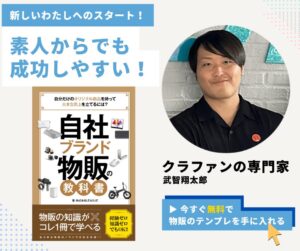
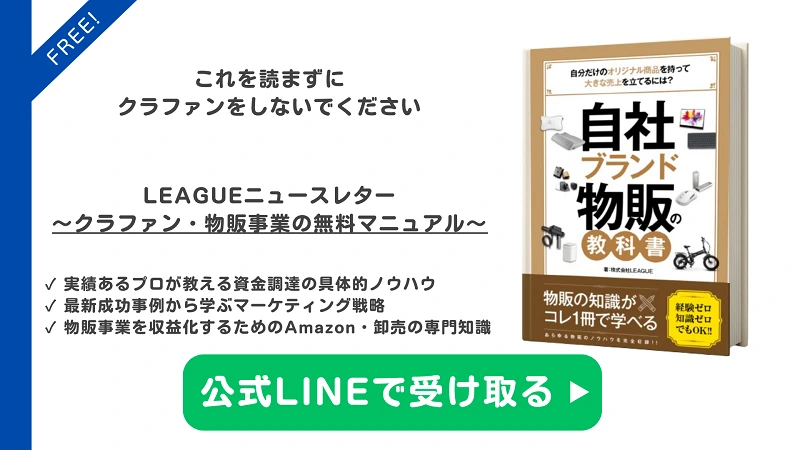


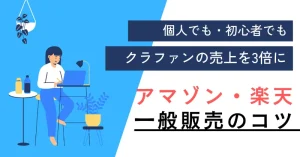




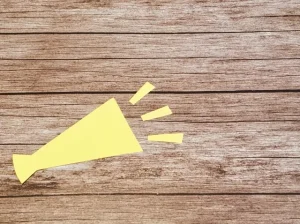

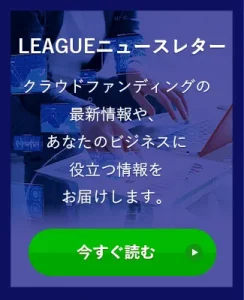
コメント