
資金調達には銀行や投資家に協力を募るしかないのかな?
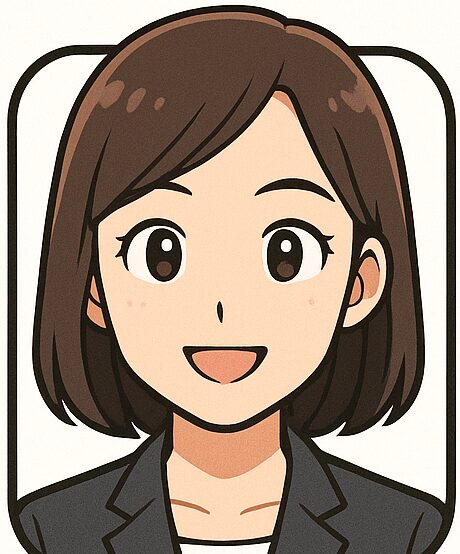
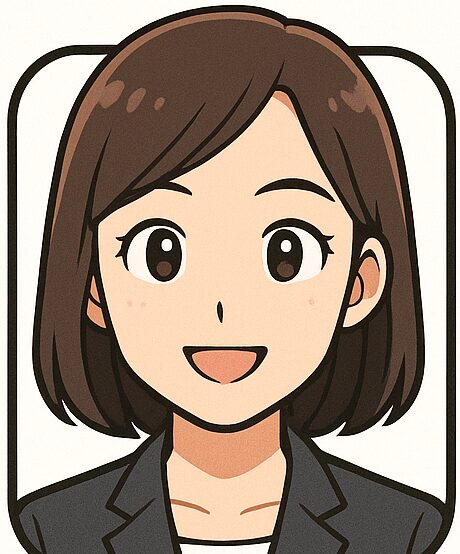
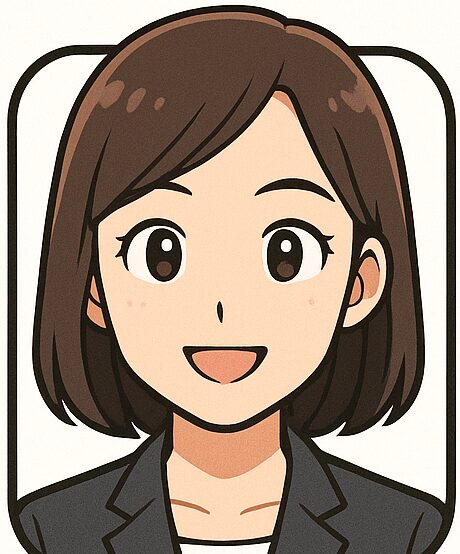
いや、最近は別の方法もあるんだよ!
地域や顧客とつながりながら資金を集めるクラウドファンディングという選択肢が、特に中小企業の間で注目されています。
この方法を見事に活用したのが、横浜DeNAベイスターズ。
2024年の優勝パレード開催のためのクラウドファンディングはファンの心をつかみ、約半月という短期間で目標の5倍・5700万円もの支援を達成しました。
ベイスターズの取り組みには、単なる資金集めを超えて、中小企業でも実践できる数々のヒントが詰まっています。この記事では、その成功のポイントをわかりやすく解説していきます。
ベイスターズが“あえて”クラウドファンディングを選んだ理由


2024年、26年ぶりに日本一となったベイスターズ。
その喜びを地域全体で祝うため、横浜の中心部で優勝パレードを実施する計画が立ち上がりました。
とはいえ、安全な運営には多額の費用がかかります。警備、交通整理、演出など、見積もりは1億円規模。資金調達の方法として球団が選んだのが、クラウドファンディングでした。
クラウドファンディングでの資金調達は、一緒につくるという感覚を支援者に持ってもらうことができます。
球団のファンにとっては、好きなチームのイベントを自分の手で支える機会にもなり、まさに共感と参加を同時に得られるアプローチでした。
クラウドファンディングの実施概要


このプロジェクトは11月中旬から約3週間、「CAMPFIRE」というプラットフォームを使って行われました。
最初の目標は1,000万円。
しかし開始すると5,700万円以上の支援が集まり、支援者数は3,600人を超えメディアでも大きく取り上げられました。
ファンの心を動かした“特別なリターン”の設計とは?
クラウドファンディングが成功するかどうかは、支援者に「応援したい」と思わせる理由をつくれるかどうかにかかっています。その鍵となるのがリターンの内容です。
横浜DeNAベイスターズが行ったプロジェクトでは、ファンの心を動かす体験型リターンが多く用意され、大きな反響を呼びました。
選手と触れ合える体験が支援の動機に


1万円の支援で選べたのは選手とハイタッチできる権利。
これはパレード終了後に特設エリアで実施され、支援者限定で選手たちと直接触れ合える特典として注目されました。


10万円の支援ではパレード行進に参加できる権利もあり、選手と同じ車列で歩けるという、ファンにとってはまさに夢のような企画が用意されていました。


中でも最も話題となったのは、300万円の番長リムジンパーティー。三浦大輔監督本人とラグジュアリーな時間を過ごすというもので、限定1組・最大4名という特別感と希少性が支援意欲を後押ししました。
このように、金額に見合った非日常体験を用意することで、支援者の満足度と参加価値が大きく高まりました。
モノではなく“思い出”を届ける発想


今回のプロジェクトでのリターンは、物品よりも体験に重きが置かれていました。
もちろん、選手のサイン入りグッズやパレード記念の手旗なども提供されましたが、メインは支援によって特別な時間を過ごせる設計にあります。
これは中小企業でも応用可能です。例えば、商品開発に協力できる体験、限定イベントへの招待、職人の現場を見学できるツアーなど、その場限りの特別な時間を用意することで、リターンの魅力がぐっと高まります。
限定性とストーリー性が支援を後押し
ベイスターズのリターンにはすべて今しか手に入らないという強い限定性があります。さらに、26年ぶりの優勝というドラマティックな背景と、「ファンと一緒に祝いたい」というストーリーが重なることで、支援者の感情に火をつけたのです。
中小企業にとっても、「この時期だけ」「この人数限定」といった特別感や、自社のストーリーに共感してもらう設計は、クラウドファンディング成功の大きなヒントになるはずです。
ベイスターズの事例から学べる5つのポイント


参照:ベイスターズ公式HP|パレードギャラリー
クラウドファンディングというと資金を集める方法という印象が強いかもしれません。
でも実は、それだけではありません。プロジェクトを通じて企業の思いや姿勢を世の中に伝えたり、ファンや地域との新しい関係を築いたりする力も、この仕組みには秘められています。
2024年に横浜DeNAベイスターズが行ったクラウドファンディングには、共感を集めるための工夫があちこちに散りばめられていました。そこからは、中小企業や個人事業でも活かせるヒントが見えてきます。
ここでは、その中でも特に実践しやすい5つの視点を紹介します。自社でクラウドファンディングを始める際の参考にしてみてください。
なぜやるのかを、ていねいに言葉にする
まず大切なのは、このプロジェクトは何のためにあるのかを自分の言葉で語ること。目的や想いが曖昧なままだと、応援したい気持ちも生まれにくくなります。
ベイスターズの例では、ファンと一緒に喜びを分かち合いたいという想いが軸にありました。支援者はその姿勢に共感し、自分もその一部になりたいと感じたのです。
「応援する」から「一緒につくる」へ
支援者を単なるスポンサーにとどめず、参加者として迎え入れる。そのためには、体験型のリターンが効果的です。
ベイスターズは、パレードを一緒に歩けるプランや、選手とハイタッチできる機会を用意しました。
中小企業でも試作品の先行体験や、限定イベントへの招待など、一緒に楽しむ場をリターンに盛り込むといいでしょう。
信頼は地域とのつながりから生まれる
プロジェクトに対する信頼感を高めたいなら、地域の機関や団体と連携するのも有効です。
ベイスターズのパレードでは、横浜市や商工会議所とタッグを組んで実施されました。
これは、行政と民間が一緒に動いているという安心感につながります。
地域で活動している中小企業にとっても、同じような連携はきっと心強い後押しになるはずです。
こまめな発信が、共感を深めていく
プロジェクトを立ち上げた後に重要になるのが、定期的な情報の発信。
支援してくれた人たちは、「その後どうなったのか?」という過程にも関心を持っています。
ベイスターズはSNSや公式ページなどを使い、進捗状況を丁寧に伝えていました。この姿勢が、応援したいという気持ちをさらに強くしていたのです。
目標を超えた未来のビジョンも共有する
クラウドファンディングは、目標金額を達成したら終わりではありません。
そのあとに「この先、何をめざすのか」「どう広げていくのか」を共有することで、支援者とのつながりはさらに深まっていきます。
横浜DeNAベイスターズも、パレード後に公式サイトを通じて写真や動画を公開し、プロジェクトの達成をすべてのファンと分かち合いました。
これにより、支援できなかった人にも喜びが届き、また応援したいと思わせる流れが自然に生まれていました。
クラウドファンディングは、単に資金を集めるだけの取り組みではありません。
支援を通じて生まれたつながりを、その後の活動や展開へどう活かすかが、次のステップに続くのです。
初めてでも大丈夫。準備から始動までの基本ステップ


はじめにやるべきことは、「なぜ資金が必要か」「どんな形で支援者に返すのか」をしっかり決めることです。
そのうえで、写真や短い動画を活用し、プロジェクトの魅力が視覚からも伝わるようにしましょう。
リターンは、1,000円台のライトな支援から、3万円や10万円といった特別な体験まで、複数の価格帯を設けるのが理想。
事前にLINEやメルマガ、SNSで周知を行い、スタート時の初動を強くするのが成功への近道です。


クラウドファンディングはつながりを育てるチャンス


横浜DeNAベイスターズの取り組みから、クラウドファンディングは資金を集めるための場所というよりも、共感を通じて人とつながる場であることがわかります。
支援者は単に見返りが欲しくて支援するのではありません。「このプロジェクトの一員になりたい」と思えたとき、自発的に動いてくれるものなのです。
あなたのビジネスにも、そうした仲間になってくれる人はきっといます。
大切なのは、まずなぜその取り組みをしたいのかを丁寧に言葉にして、誰にその思いを届けたいのかを考えること。それがスタートラインになります。
もし「やってみたいけど、何から始めればいいのか分からない」と感じたら、LEAGUEにご相談ください。成功事例の紹介や、企画設計のアドバイスなど、あなたの挑戦を具体的にサポートいたします。新たな一歩を踏み出すきっかけとして、ぜひ私たちの知見をご活用ください。


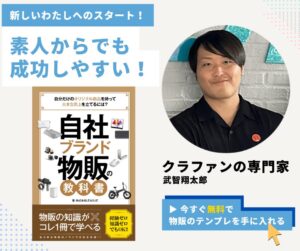
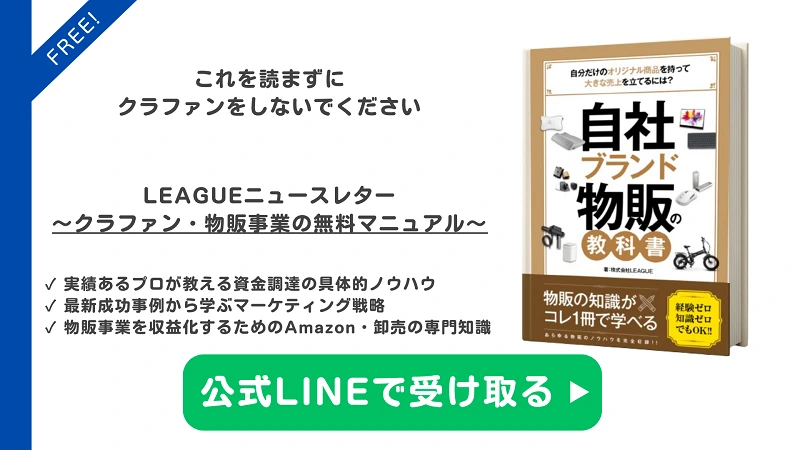

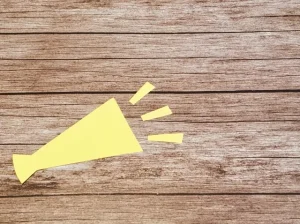
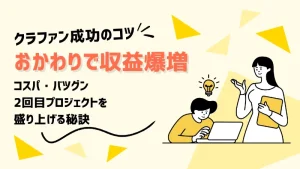





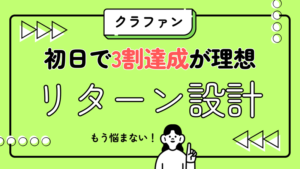

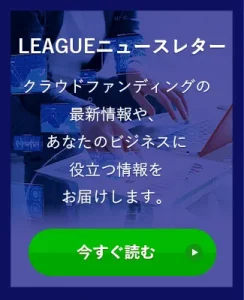
コメント