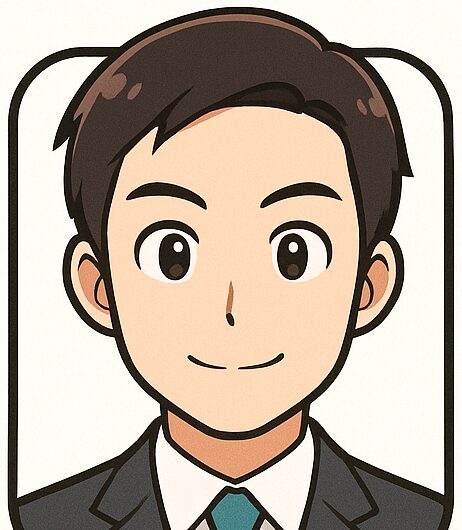
助成金や補助金などの支援金制度を使えるなら活用したい。クラファンでも使えるの?
クラウドファンディングは、資金がなくても新しい商品やサービスを世に出すことができる強力な手段です。しかし、実際に取り組もうとすると、製造費や商品の輸送費、プラットフォームの手数料やWeb広告費、ページ制作費など、プロジェクトの準備や実行には意外とコストがかかるものです。
そこで活用したいのが、助成金や補助金です。
国や自治体が提供する助成金・補助金を利用すれば、手数料の負担を軽減したり、プロジェクト全体の経済的な持続可能性を高めたりすることが可能です。
この記事では、クラウドファンディングに挑戦したい中小企業の経営者や個人事業主の皆様に向けて、
- クラウドファンディングと助成金・補助金の関係性
- 併用できる具体的な助成金・補助金の種類
- 申請から受給までの流れ
- 活用する上での注意点
などを具体例を交えながら解説します。
クラウドファンディングと助成金・補助金の関係性


ここではまず、クラウドファンディングに助成金や補助金がなぜ必要なのかについて、具体的なコスト例を交えながら解説していきます。
助成金・補助金が必要なのか
クラウドファンディングは魅力的な資金調達手段ですが、それだけで全ての費用を賄えるとは限りません。目標金額を達成しても、プラットフォーム利用手数料(一般的に調達額の10〜20%程度)や決済手数料、リターン(返礼品)の制作・発送費用、広告宣伝費など、様々な経費が発生します。
例
100万円の資金調達に成功しても、手数料で15万円、リターン費用で20万円かかると、実際に事業に使える資金は65万円になってしまう、といったケースです。
また、クラウドファンディングはプロジェクトが魅力的でなければ資金が集まらない可能性もあります。
そこで、助成金や補助金を活用することで、これらの費用負担を軽減したり、クラウドファンディング実施後の不足分資金を確保したりと、より安定した資金計画を立てることが可能になります。自己資金の負担を減らし、より多くの資金を事業そのものに投下できるようになるのです。
対象となる経費例
クラウドファンディングを実施する際にはさまざまな費用が発生しますが、これらを経費として補助金申請することにより、費用の自己負担を大幅に軽減できます。以下、補助金申請の対象となる主な経費を詳しく解説します。
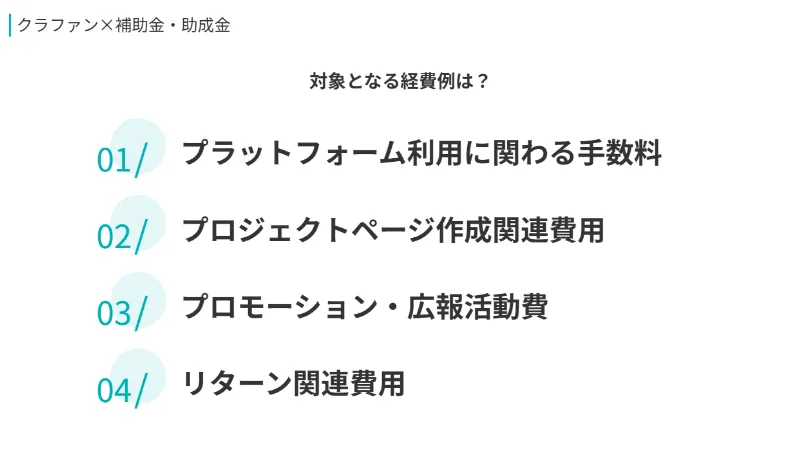
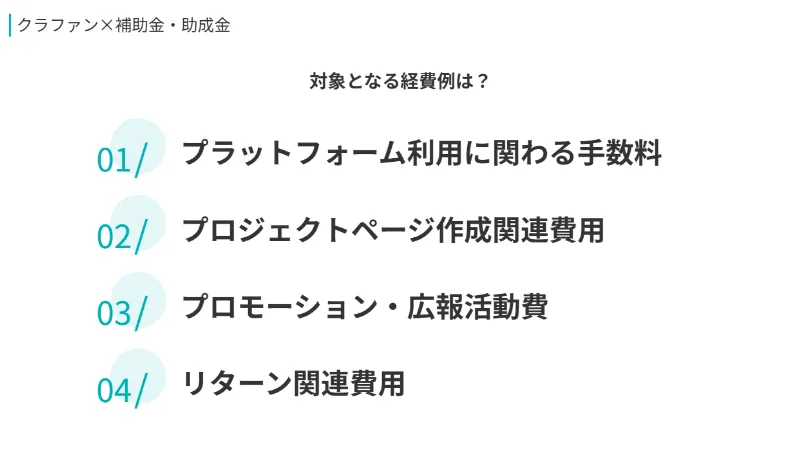
プラットフォーム利用に関わる手数料
プラットフォーム利用料はクラウドファンディングサイトに支払う利用手数料(通常10~20%)や決済手数料(2~5%)のことです。
たとえば、100万円の支援を集めた場合、最大25万円近くの手数料が発生します。
主な対象費用
- 掲載手数料/利用手数料(調達額の10~20%程度)
- 決済手数料(クレジットカード決済等、通常2~5%)
- 早期振込手数料(資金の早期受取にかかる費用)
これらは東京都クラウドファンディング活用助成金など多くの自治体の制度で明確に対象経費として認められています。
プロジェクトページ作成関連費用
プロジェクトページ作成費用は、ページデザイン、画像作成、ライティング、映像制作など、クラウドファンディングのプロジェクトページ作成にかかる費用のことです。
たとえば、プロのデザイナーやライターに依頼した場合、10万円以上の制作費がかかることもありますが、補助金を活用すれば最大2/3が支援されるケースもあります。
主な対象費用
- ページのデザイン・構成委託費
- 画像・動画制作費
- 文章作成費(専門家やライターへの外注費)
- 写真撮影費(商品やサービスの撮影)
これらの費用はプロジェクトの成功率に直結する重要な要素であり、多くの補助金制度で対象として認められています。
プロモーション・広報活動費
広報・広告費用はSNSやWeb広告、地域メディアでの広報活動にかかる費用も対象となります。
たとえば、広告に20万円かけた場合、2/3の補助を受ければ実質負担は約7万円程度に抑えることができます。
主な対象費用
- SNS広告費、Web広告費
- 印刷物制作費(チラシ・ポスターなど)
- 実店舗での展示やイベント開催費用
- プロモーションイベント費用
荒川区のクラウドファンディング活用支援補助金では、プロジェクトを周知するための印刷物制作委託費や広告宣伝費が明示的に対象経費として挙げられています。
リターン関連費用
リターン関連費用は支援者へのリターン(返礼品)提供に関わる費用のことです。ただし、補助金制度によって対象となる範囲が異なるため注意が必要です。
主な対象費用
- リターン製作費
- パッケージング費用
- 発送・配送費
- 梱包資材費
これらの費用は、プロジェクト実施に不可欠な費用として認められる傾向がありますが、制度によっては対象外となる場合もあります。
申請できない主な経費
以下の経費は一般的に補助対象外となります。
対象外の費用
- 申請したプロジェクト以外の経費
- 対象外のクラウドファンディングサイトに支払った経費
- 複数プロジェクトにまたがる包括的なサービス費用
- 手数料に含まれる消費税
- 過去に同一プロジェクトで助成金を受けた場合の再申請分
クラウドファンディング向けの補助金では、経費の一部が補助率(1/2~3/4)に基づいて支援されるため、結果的にかかった費用を半分以下に削減できる可能性があります。
事業のスタート時点でコストを抑えながら、効果的にクラウドファンディングを展開するためにも、補助金の活用を前向きに検討してみましょう。
ただし、各補助金制度によって対象となる経費や補助率は異なりますので、申請前に詳細を確認することが重要です。
助成金・補助金活用のメリット
クラウドファンディングと助成金・補助金を併用することには、以下のようなメリットがあります。
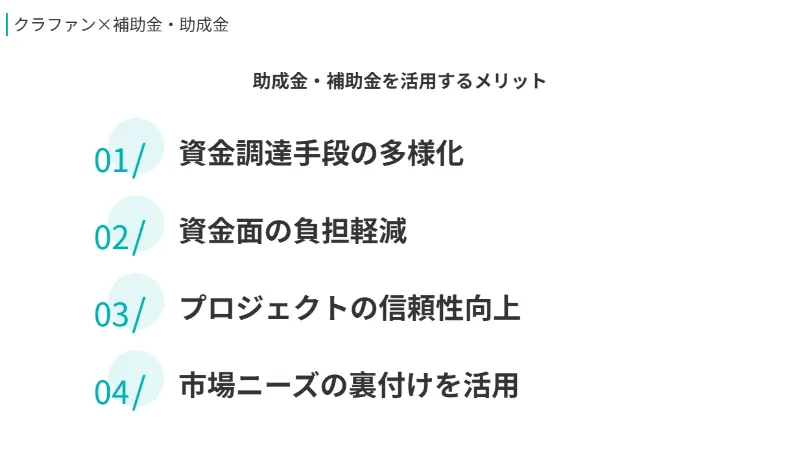
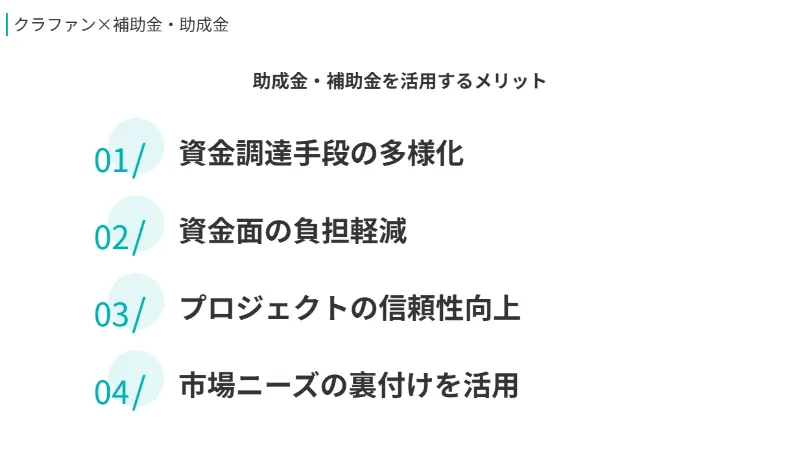
資金調達手段の多様化と負担軽減
クラウドファンディング(主に購入型)は資金の前払い、補助金は原則後払い(精算払い)という特徴があります。
先にクラウドファンディングで運転資金を確保しつつ、設備投資などの大きな支出は補助金でカバーするなど、両者を組み合わせることで資金繰りを安定させることができます。
プロジェクトの信頼性向上
国や自治体の審査を経て採択される助成金・補助金は、事業計画の客観的な評価を受けた証となります。
これは、金融機関からの融資審査や、クラウドファンディングの支援者に対する信頼性を高める効果が期待できます。
市場ニーズの裏付け
補助金申請の際、クラウドファンディングでの支援実績(特に目標達成した場合)を提示することで、市場から求められている事業であるという強力なアピールポイントになります。
これにより、補助金の採択率向上に繋がる可能性があります。
クラウドファンディングと併用可能な一般的な補助金制度
クラウドファンディングに特化したものでなくても、事業目的や経費内容が合致すれば併用できる一般的な補助金・助成金は多数存在します。ここでは代表的な制度を4つご紹介します。
小規模事業者持続化補助金
持続化補助金として広く知られており、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する、非常に人気の高い補助金です。
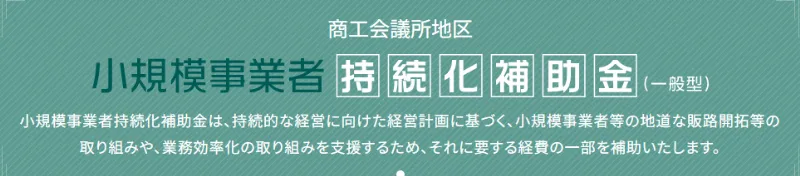
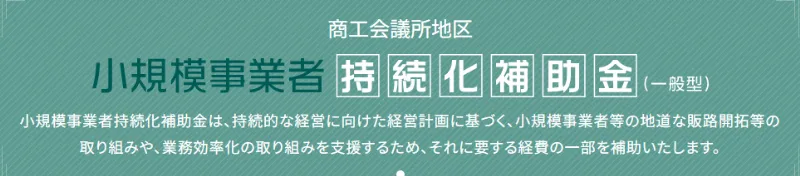
クラウドファンディングとの相性も抜群で、新商品をクラウドファンディングで世に出す際のプロモーション費用やパッケージデザイン費などに利用できます。
個人事業主・フリーランス:従業員5人以下
小売業・サービス業:従業員5人以下
製造業・その他:従業員20人以下
| 広報費 | チラシ作成、広告掲載、クラウドファンディングページのPRなど |
| ウェブサイト関連費 | クラウドファンディングと連携するECサイト構築、LP作成など |
| 開発費 | 新商品・サービスの試作開発、リターン品の開発など |
| 展示会等出展費 | クラウドファンディングで開発した商品の展示会出展費用など |
通常枠:上限50万円(補助率2/3)
創業枠:上限200万円(補助率2/3)
賃上げ枠:上限200万円(補助率2/3)
新しい商品を開発し、クラウドファンディングで先行販売。そのプロモーション費用(Web広告、LP制作)や、リターン品のデザイン費用を持続化補助金で賄いましょう。
クラウドファンディングでの実績を申請書に盛り込むことで、販路開拓の具体性や市場ニーズをアピールでき、採択時に有利に働きます。
IT導入補助金
中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助し、業務効率化や売上アップをサポートする制度です。


クラウドファンディングで成功した商品を自社のネットショップでも販売したい場合、その構築費用にIT導入補助金を活用できます。
また、プロジェクト管理ツールや支援者とのやりとりを効率化するITツールの導入費も補助対象になるケースがあります。
中小企業・小規模事業者
医療法人・社会福祉法人等
| ソフトウェア購入費、クラウド利用料 | ECサイト構築ツール、顧客管理システム(CRM) 決済システムなど |
| 導入関連費用 | クラウドファンディングと連携するECサイト構築 LP作成など |
通常枠:5万円~450万円(補助率1/2)
デジタル化基盤導入枠:5万円~350万円(補助率3/4~2/3)
セキュリティ対策推進枠:5万円~100万円(補助率1/2)
クラウドファンディングで購入予約を受け付けた後、本格的な販売に移行するためのECサイト構築費用や、支援者(顧客)管理のためのCRMツール導入費用に活用する。
不動産投資型クラウドファンディングシステムの導入に活用された事例もあります。
IT導入支援事業者との連携が必須となります。導入したいツールが補助対象か、またどの申請枠が適しているか、事前に相談しましょう。
ものづくり補助金
正式名称は、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金です。
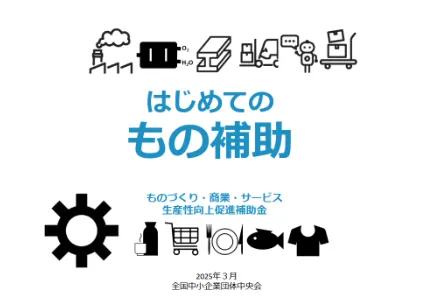
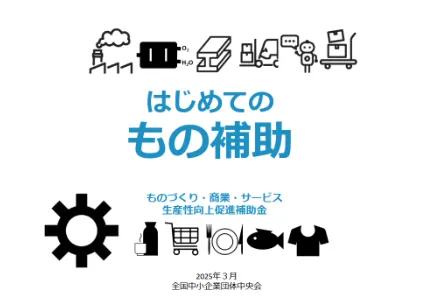
中小企業・小規模事業者等が取り組む、革新的な製品・サービス開発や生産プロセス改善のための設備投資などを支援する制度です。
クラウドファンディングでは、まだ市場にない新しい製品を発表することが多いため、ものづくり補助金と併用することで、開発と販売の両面で支援が受けられます。
中小企業・小規模事業者
個人事業主
- 機械装置・システム構築費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
一般型:100万円~1,250万円(補助率1/2、小規模事業者等は2/3)
グローバル展開型:1,000万円~3,000万円(補助率1/2)
クラウドファンディングで試作品を発表し、支援が集まった革新的な製品を量産するための製造設備導入費用に活用する。
革新性が求められるため、単なる仕入れ販売ではなく、自社で開発・製造を行う場合に適しています。事業計画の策定ハードルはやや高めですが、大きな設備投資が必要な場合に有効です
展示会助成金
展示会助成金という名称の国レベルの単一制度はありませんが、多くの自治体や支援機関が、国内外の展示会への出展費用を補助する制度を設けています。
また、小規模事業者持続化補助金の対象経費にも展示会等出展費が含まれています。
クラウドファンディング後に商品をより多くの人に知ってもらう手段として、展示会出展は非常に効果的です。助成金を活用すれば、ブース設営費や資料作成費の負担を減らせます。
中小企業・小規模事業者
- 出展小間料
- 装飾費
- 運搬費
- 通訳費
国内展示会:上限30万円~50万円(補助率1/2など)
海外展示会:上限100万円~150万円(補助率1/2など)
※地域や実施団体により異なります
クラウドファンディングで開発した製品の実物を多くの人に見てもらい、販路を拡大するために展示会に出展する。その際の出展料、ブース設営費、関連資料作成費などに助成金・補助金を活用する。
自社の所在地にある自治体や、取引のある金融機関、商工会議所などが提供する支援制度を調べてみましょう。
東京都中小企業振興公社:東京都
大阪府商工労働部:大阪
クラウドファンディング専用の助成金・補助金
クラウドファンディングの実施に特化した、あるいは非常に親和性の高い助成金・補助金も存在します。特に自治体が設けているケースが多いため、個別にリサーチすることをおすすめします。
クラウドファンディング活用助成金
東京都クラウドファンディング活用助成金
東京都にて事業者に向けた公的助成制度です。
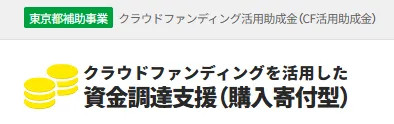
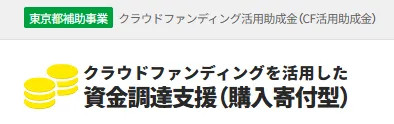
購入型・寄付型クラウドファンディングを活用して資金調達を行う都内中小企業者等に対し、プラットフォーム事業者へ支払う手数料や広報費用を助成します。
- 東京都内で事業を行う、または行う計画のある創業希望者・事業者
- 中小企業基本法に規定する中小企業者、個人事業主、NPO法人、社団・財団法人、創業前の個人等
- 大企業が実質的に経営を支配していないこと
- 取扱クラウドファンディング事業者のサイトでプロジェクトを掲載・成功させたことがある
- 利用手数料、決済手数料、早期振込手数料
- プロジェクトページ作成費用
- プロジェクトの広報活動費用
1/2補助区分:助成率2分の1、上限80万円(創業、新製品・新サービス開発、ソーシャルビジネス)
2/3補助区分:助成率3分の2、上限100万円(社会的課題解決、環境配慮、デジタル活用、事業再構築)
手数料負担を直接軽減できるため、クラウドファンディング実施のハードルを下げることができます。年度内に4回まで申請をおこなえます。
東京都中小企業振興公社クラウドファンディング活用支援
こちらは直接的な助成金とは少し異なりますが、同公社の中小企業ニューマーケット開拓支援事業の採択企業を対象に、クラウドファンディング実施をトータルでサポートする制度です。
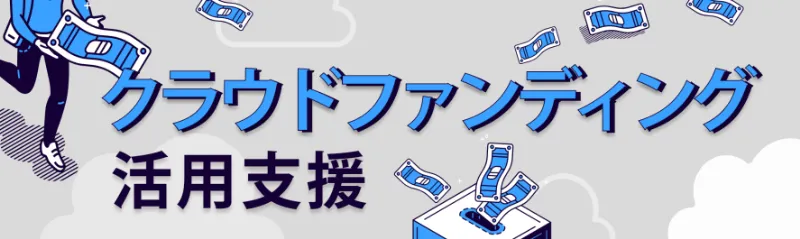
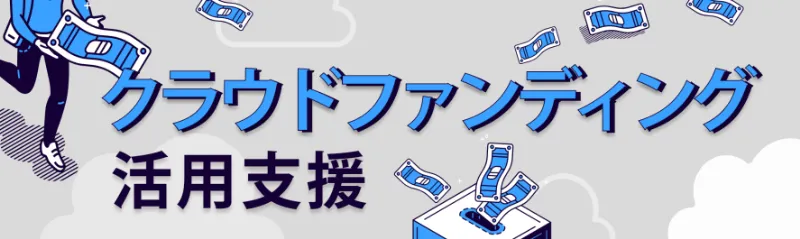
中小企業ニューマーケット開拓支援事業の支援企業
- 専任アドバイザーによるプロジェクト実行支援
- クラウドファンディング手数料の2分の1(上限40万円)を公社が負担
- 実店舗への展示などプロジェクトのPR支援
- 専用サイトでの集合企画としての訴求
自治体独自のクラウドファンディング支援制度
各自治体が、地域活性化や産業振興を目的に、独自のクラウドファンディング支援制度を設けている場合があります。
かすみがうら市クラウドファンディング活用支援事業補助金
かすみがうら市内の産業振興や地域活性化を目的として、クラウドファンディングを活用する個人・法人・団体等に対し、クラウドファンディング実施時にかかる経費の一部を補助する制度です。


個人事業者(開業予定者も含む)、法人(設立予定者も含む)、団体、学生
住所・所在地は問わず、市内でプロジェクトを実施または計画していること
寄附型または購入型
All in方式または All or Nothing方式
- クラウドファンディング運営事業者に支払う利用手数料
- プロジェクトページ作成費用
補助対象経費の10/10(上限50万円)
同一の対象者による申請は年1回まで
新事業展開テイクオフ支援事業補助金(大阪)
大阪府全域を対象とした、中小企業の新たな事業展開や生産性向上を支援する補助金です。公式HP
大阪府内に事業所を有する中小企業者
- 広告宣伝・販売促進費(クラウドファンディングのプロモーション費用に充当可能)
- 機械装置等費
- 外注費
最大100万円(人手不足解消に取り組む特定の業種には150万円まで)
補助率は対象経費の1/2
特定対象者向けの助成金・補助金
特定の属性を持つ起業家や事業者を対象とした、より手厚い支援制度も存在します。これらもクラウドファンディングと組み合わせることが可能です。
女性起業家支援事業
各自治体や政府系機関、民間財団などが、女性の起業を支援するための助成金・補助金、融資制度、コンサルティングなどを提供しています。
起業初期に必要となる広告費、設備費、人件費などが対象で、クラウドファンディングと組み合わせることで効果的な立ち上げが可能になります。
女性であること
これから起業する方、または起業後間もない方(概ね5年以内)
- 創業時の経費に対する補助金(上限額100万円程度、補助率1/2~2/3)
- 専門家によるアドバイス
- 起業塾や交流会などのソフト支援
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業:東京都
女性、若者/シニア起業家支援資金:日本政策金融公庫
一般的な補助金に加え、女性向け支援を併用することで、より有利な条件で資金調達やサポートを受けられる可能性があります。
若者・シニア向け起業支援制度
29歳以下の若者や、定年退職後の再チャレンジを目指す60歳以上のシニア世代に対して、年齢層ごとに起業を支援する制度も各自治体に用意されています。
クラウドファンディングと組み合わせて効果的な起業支援が可能です。
若者(概ね35歳未満)またはシニア(概ね55歳以上)
これから起業する方、または起業後間もない方
- 創業時の経費に対する補助金(上限額50万円~200万円、補助率1/2~2/3)
- 専門家によるメンタリング
- ビジネスプランコンテストへの参加機会
女性、若者/シニア起業家支援資金:日本政策金融公庫
TOKYO創業ステーションの各種プログラム:東京
年齢要件に該当する場合は、これらの制度を活用できないか検討しましょう。創業セミナーや専門家相談がセットになっている場合も多いです。
社会課題解決型スタートアップ支援事業
NPO法人やソーシャルビジネス事業者など、社会的な課題解決を目的とした事業に対して、資金援助や経営支援を行うプログラムにむけて、各地域ごとに支援サービスが展開されています。
社会性の高いクラウドファンディングプロジェクトと相性が良いでしょう。
社会課題(環境、福祉、教育、地域活性化など)の解決に取り組むスタートアップ
法人格の有無は問わない場合が多い
事業化に必要な経費の補助(上限額300万円程度、補助率2/3)
専門家によるハンズオンサポート
ピッチイベントなどの機会提供
寄付型クラウドファンディングや、社会貢献性の高い購入型クラウドファンディングとの親和性が高い分野です。事業の社会的意義を明確にすることで、支援を得やすくなります。
申請から受給までの流れ
助成金・補助金の申請プロセスは制度によって異なりますが、一般的な流れを理解しておきましょう。
申請前の準備
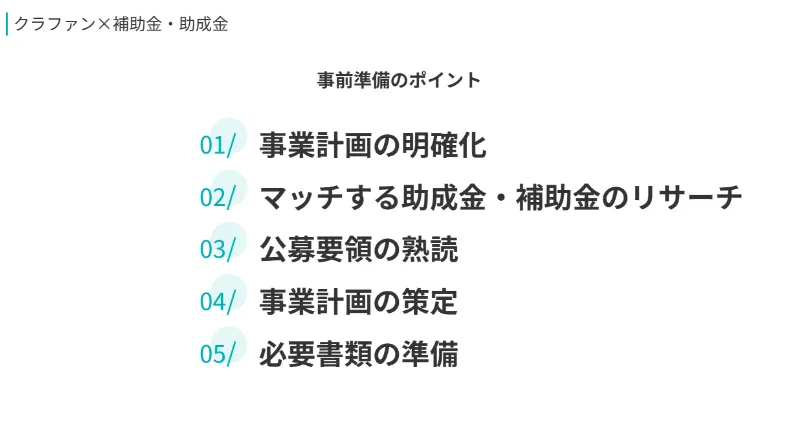
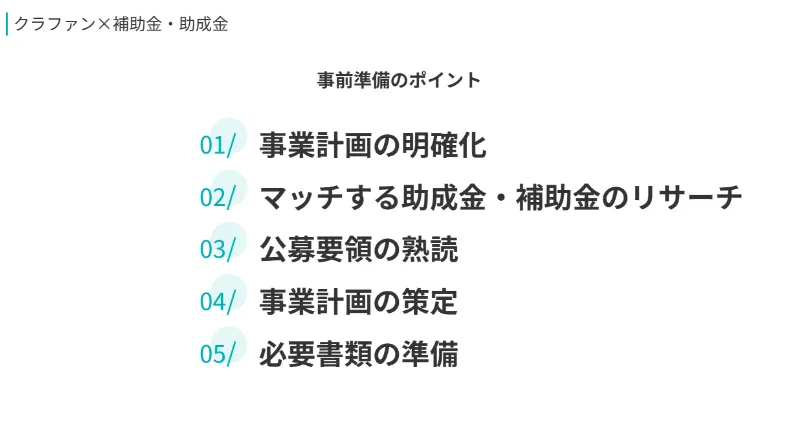
- 事業計画の明確化
-
目標、ターゲット、提供価値、収益モデルなどを明確にします。特に、クラウドファンディングとの関連性や相乗効果を明示できると良いでしょう。
- マッチする助成金・補助金のリサーチ
-
ご自身の事業内容や目的に合った助成金・補助金を探します。国(中小企業庁「ミラサポplus」など)、都道府県、市区町村、商工会議所・商工会、金融機関などのウェブサイトを確認しましょう。
- 公募要領の熟読
-
利用したい制度が見つかったら、必ず「公募要領」を隅々まで読み込みます。対象者、対象経費、補助額・補助率、申請要件、スケジュールなどを正確に把握することが重要です。
- 事業計画の策定
-
ほとんどの補助金では、事業計画書の提出が求められます。クラウドファンディングの計画も含め、事業の目的、内容、実施体制、資金計画、期待される効果などを具体的にまとめます。
- 必要書類の準備
-
履歴事項全部証明書(法人の場合)、決算書、本人確認書類(個人の場合)など、必要な書類を事前に準備します。
特に見積書は、クラウドファンディングプラットフォームから取得しておく必要があります。
- GビズIDプライムアカウントの取得
-
近年、多くの補助金申請が電子申請システム・Jグランツで行われており、その利用にはGビズIDプライムアカウントが必要です。取得には2〜3週間かかる場合もあるため、早めに申請しておきましょう。
申請書の作成ポイント
申請書では、審査員に実現性・継続性・社会性といったポイントをわかりやすく、伝わるように書くことが求められます。採択される申請書を作成するには、以下の点を意識しましょう。
目的の明確化
なぜこの事業が必要なのか、補助金を使って何を実現したいのかを明確に伝えます。
具体性と実現可能性
事業計画は具体的に、かつ実現可能な内容で記述します。スケジュールや数値目標も盛り込みましょう。
補助金の必要性
なぜ補助金が必要なのか、自己資金や他の調達手段だけでは不足する理由を説明します。
事業の強み・独自性
他社との違いや、自社の強みをアピールします。(クラウドファンディングでの先行予約数なども有効なアピール材料になります)
加点要素の確認
公募要領に記載されている加点項目(賃上げ、事業承継、特定の認証取得など)があれば、積極的に取り組み、申請書でアピールします。
分かりやすさ
審査員は必ずしもその分野の専門家ではありません。専門用語を避け、図やグラフを用いるなど、分かりやすく記述することを心がけます。
申請後の流れ
審査から補助金受給までの一般的な流れは以下の通りです。
公募期間内に、指定された方法(電子申請、郵送など)で申請書類を提出します。
事務局による書類審査や、場合によってはヒアリング(面接)が行われます。審査期間は制度により数週間〜数ヶ月かかります。
審査結果が通知されます。
申請が審査を通過し、補助金や助成金の対象事業として採択された場合、採択通知や交付決定通知が書面またはメールで届きます。
書類に不備や不足、記載ミスなどがあった場合、差し戻しや修正依頼の通知がメールや電話で届きます。
残念ながら審査を通過できなかった場合、「不採択通知」や「審査結果通知」が届きます。多くの場合、事務的な内容で理由が明記されないことが一般的です。
採択された場合、補助金の交付を受けるための手続き(交付申請)を行います。内容が承認されると「交付決定通知」が届き、ここで初めて補助対象事業を開始できます。
交付決定前に発生した経費は原則対象外となるため注意が必要です
策定した事業計画に基づき、補助対象事業を実施します。経費の支払いに関する書類(見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、領収書/振込控など)は全て保管しておきます。
事業完了後、定められた期間内に、事業の結果や経費の内訳などをまとめた「実績報告書」と証拠書類を提出します。
実績報告書の内容が審査され、補助金の金額が最終的に確定します。
確定した金額に基づき補助金の請求を行い、指定した口座に補助金が振り込まれます(精算払い)。
通常、事業完了から補助金受給まで2~3ヶ月かかることを見込んでおく必要があります。
補助金によっては、事業完了後も数年間にわたり、事業の状況報告などが求められる場合があります。必要書類は保管しておき、必要時に提出できるようにしておきましょう。
助成金・補助金を併用する際の注意点
クラウドファンディングと助成金・補助金の併用には大きなメリットがありますが、同時に注意すべき点も存在します。
経費の重複申請はNG
経費の重複申請は、最も重要な注意点の一つです。
同じ経費に対して、複数の補助金や助成金を重複して申請・受給することは認められていません。これは不正受給とみなされ、補助金の返還に加え、加算金の支払いや今後の申請資格の停止など、厳しいペナルティが課される可能性があります。
例
クラウドファンディングの手数料に対して、東京都のクラウドファンディング活用助成金と小規模事業者持続化補助金の両方を同時に申請することはできません。
対策
どの経費をどの制度で申請するのか、明確に区分した資金計画を立てることが不可欠です。エクセルなどで管理表を作成し、申請前や実績報告時に重複が発生しないよう、細心の注意を払いましょう。
補助金は後払い
多くの補助金・助成金は、事業を実施し、経費を支払った後に、実績報告を経て交付される後払い(精算払い) です。
対策
補助金が振り込まれるまでの間は、自己資金や融資などで経費を立て替える必要があります。クラウドファンディングで調達した資金も活用できますが、資金繰りの計画をしっかり立てておくことが重要です。
事業期間外に支出した経費は対象外
補助金や助成金を活用する際、対象となる経費は補助事業実施期間内に発生し、支払われたものに限られます。
この期間は、交付決定日から実績報告の提出期限までと定められており、期間外に発生した経費は原則として補助対象外となります。たとえ事業に必要な支出であっても、期間外に発注や支払いが行われた場合、補助金の対象とはなりません 。
対策
事業計画を立てる際には、補助事業実施期間を十分に確認し、スケジュール管理を徹底しましょう。また、やむを得ず期間外に支払いが発生する可能性がある場合は、事前に事務局へ相談し、適切な対応を取ることが重要です。
制度に詳しい専門家への相談
補助金・助成金制度は種類が多く、内容も複雑で、頻繁に更新されます。公募要領の解釈が難しい場合や、申請書の作成に不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談先例
| 商工会議所・商工会 | 地域の中小企業支援の拠点であり、無料で相談に乗ってくれることが多い。 |
| よろず支援拠点 | 国が設置する無料の経営相談所。 |
| 中小企業診断士、行政書士 | 補助金申請支援を専門に行っている場合もあります。 多くは有料。 |
| 税理士 | 顧問税理士がいれば、経理面でのアドバイスを受けられます。 |
| クラファンの専門 | クラファンに精通した専門家にもあわせて相談することで、どの費用が補助対象となるか、的確なアドバイスを受けることができます。 |
LEAGUEのクラウドファンディングサポート
当社LEAGUEでは、クラウドファンディングの企画・戦略立案・運営サポートなど、無料相談を受け付けています。クラウドファンディングの代行についても受け付けておりますので、「どこから手をつければいいか分からない…」と悩んでいる方は、成功の第一歩を踏み出しましょう。
\ 専門家がサポート /
結論(Conclusion)
クラウドファンディングでは手数料や広告費などの初期コストがかかりますが、適切な助成金・補助金を活用することで、これらの負担を大幅に軽減できます。
小規模事業者持続化補助金のような事業全般を支えるものから、東京都クラウドファンディング活用助成金のようにプラットフォーム手数料を直接補助してくれるもの、さらにはお住まいの自治体独自の支援制度まで、探してみると多くの選択肢があることがわかります。
助成金・補助金を申請する際は、経費の重複申請を避け、事業期間や申請タイミングに注意することが重要です。不明点があれば商工会議所や専門家に相談することをおすすめします。
LEAGUEは今回紹介した海外クラウドファンディングのみならず、国内クラウドファンディングにおいても多くのサポート実績があります。クラウドファンディングの企画から実施まで、無料でご相談に対応いたします。お気軽にご連絡ください。

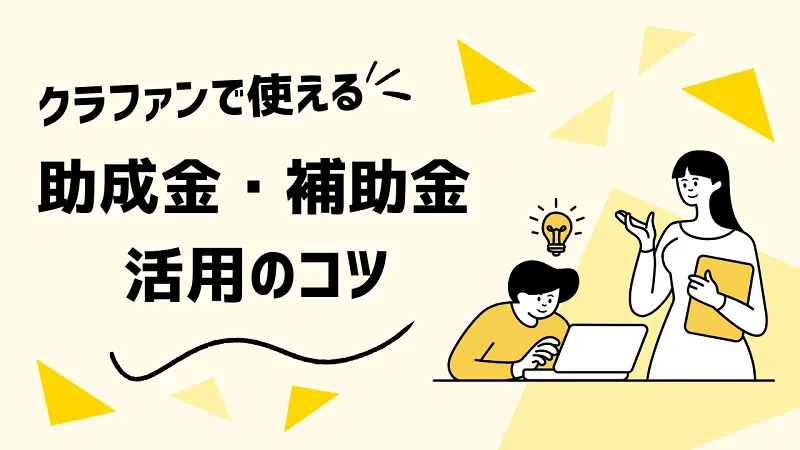
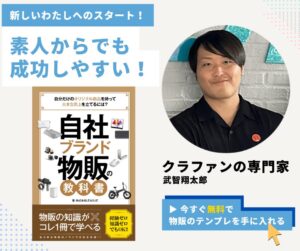
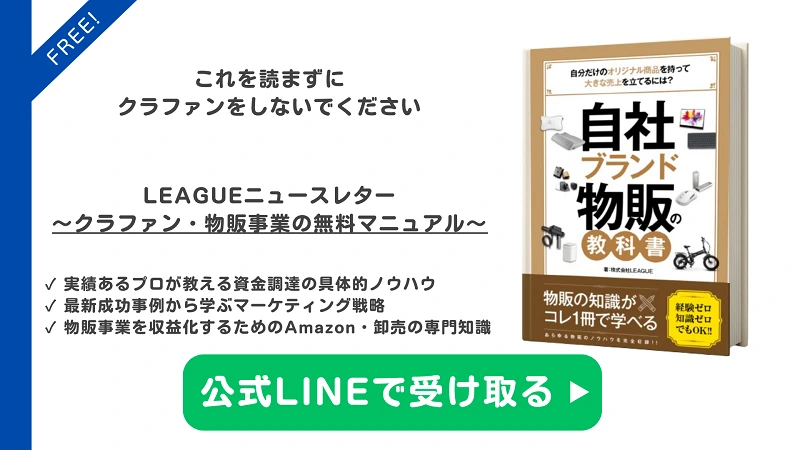




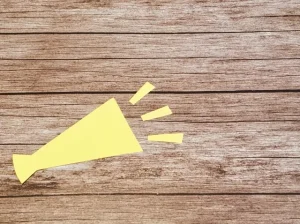
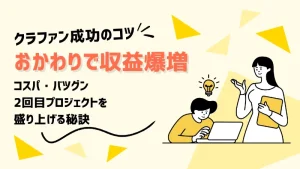





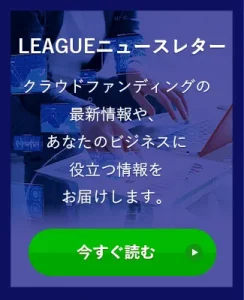
コメント