
高校生でもクラファンってできるの?
2024年夏、32年ぶりに甲子園出場を果たした島根県の大社高校。93年ぶりに悲願のベスト8という歴史的快挙を達成しました。
その快進撃の裏側には、多くの人々の想いが集まったクラウドファンディングが大きく貢献していました。
地元住民や卒業生、さらには全国のファンまで巻き込みながら進められたこのプロジェクトは、単なる「高校野球の支援」を超えた価値を生み出しました。
そしてそのプロセスには、クラウドファンディングをビジネスにも応用できるヒントが数多く詰まっています。
この記事では大社高校の挑戦を通じて、クラウドファンディングの基本から地域や顧客を巻き込むストーリー設計まで、わかりやすく解説していきます。
大社高校の甲子園出場に立ちはだかった資金の壁


2024年、島根県の大社高校が待ちに待った32年ぶりの夏の甲子園出場を決めると、地元は歓喜に包まれました。
ところが、その大きな喜びと同時に、避けては通れない現実的な課題が浮上したのです。
それが、甲子園遠征に要する莫大な資金の不足でした。
地方の学校が全国大会への出場を決めた場合、様々な費用が必要に。
- 移動費
- 宿泊費
- 応援団の経費
- その他
出場に伴う費用が想定を超える規模となり、学校関係者は頭を悩ませていました。
そんな中、地元やOB、そして全国のファンが力を合わせたクラウドファンディングが始動します。
高校野球がつないだ人々の輪


近年、スポーツの現場でクラウドファンディングを活用した資金調達が目立つようになりました。
- インターネットを介して不特定多数の人々から資金を募る仕組み
- 明確な目標金額と使い道を提示
- その理念に共感した人々からの「支援」という形で資金を集める
クラウドファンディングは商品開発や新規事業の立ち上げに留まらず、地域活性化や社会課題解決といった幅広い分野で活用されています。
大社高校も資金の支援を募るため、クラウドファンディングのプロジェクトを設立。
プロジェクトの立ち上げは、試合日程が進む中で急ピッチで行われました。目標は1,000万円。プロジェクト開始から、わずか6日で854万円以上の支援が集まり、その勢いはSNSを通じて全国へと広がっていきました。
甲子園で戦う選手たちを「最後まで全力で応援したい」。
そんな想いが地域住民や卒業生だけでなく全国のファンのたちの心を動かし、支援の輪は大きく膨らみました。
大社高校クラウドファンディングの成功要因


大社高校のクラウドファンディングが大きな成功を収めたのには、明確な理由がありました。
ここではその成功要因について解説していきます。
共感を呼ぶ力
大社高校の硬式野球部が掲げた「何が何でも甲子園」というスローガンは、多くの人々の心に響きました。
厳しい練習を経て甲子園出場という目標を現実にした彼らの姿が、支援者たちの共感を強く引き出し、多くのサポートを呼び込む力となったのです。
スピーディーな情報伝達
このプロジェクトでは、SNSや地域メディアを効果的に使い、進捗状況をリアルタイムで共有していました。
途切れることのない情報発信は、クラウドファンディングの存在を急速に広め、新たな支援層を獲得する大きなきっかけになりました。
透明性のある情報が公開されたことで支援者との信頼関係はより強固になり、さらにプロジェクトの認知度も向上に繋がったのです。
参加しやすい設計
少額からでも気軽に支援できるプロジェクト設計も、成功には欠かせない要素でした。
この工夫があったからこそ、より多くの人々が参加しやすく、結果として支援の輪は予想を超える広がりとなったのです。
大社高校に学ぶ!クラウドファンディングを成功に導く3つの工夫


大社高校の硬式野球部が実行したクラウドファンディングは、ただの資金調達ではなく、多くの人々の心を動かすプロジェクトでした。
この取り組みには、ビジネスにも取り入れられるヒントが。ここでは3つのポイントを解説します。
想いを伝える
なぜこの挑戦をしているのか。
まずはその理由を、自分自身の言葉でしっかりと伝えることが大切です。
大社高校の「何が何でも甲子園」という強い想いがのったスローガンは、地元の人たちや多くの支援者の心に響きました。数字や計画ももちろんですが、最終的に人を動かすのは、その奥にある想いです。率直な言葉こそ、共感を呼びます。
発信は「知らせる」ではなく「巻き込む」意識で
SNSでの発信を、ただの宣伝で終わらせるのはもったいないアプローチです。
クラウドファンディングは、支援してくれる人と一緒に作っていくものです。
たとえば日々の準備風景を投稿したり、支援者の名前を紹介したり、コメントに丁寧に返信したりと地道に感謝を伝えることを意識しましょう。そうやって支援者との距離を縮めることで、「応援してよかった」と感じてもらえるようになります。
プロジェクト達成後の支援者フォロー
プロジェクトが終わったあと、どんな報告をするかで支援者の印象は大きく変わります。
集まったお金がどう使われたのか、どんな結果につながったのか。
そうした情報を写真やストーリーと一緒に届けることで、支援者は自分の応援が役に立ったと実感できます。
そしてまた次も応援したい、と思ってもらえる関係が生まれるのです。
個人でも初心者でも成功する、クラウドファンディングの設計方法についてはこちらの記事で解説しています。


クラウドファンディングが拓く可能性


大社高校のクラウドファンディングが成功した背景には、単なるお金集めを超えた人と人のつながりがありました。
選手たちを応援したいという想いが、地域を越えて全国に広がり、それがまた新しい応援の輪を生んでいく。そんな連鎖が、ベスト8進出という快挙を支えていたのです。
こうした動きは、スポーツに限らずビジネスの世界にも通じるところがあります。
誰かの挑戦を、共感や応援で支える。
このクラウドファンディングの仕組みは、企業や個人が地域やお客様と信頼関係を築いていくためのヒントにもなるはずです。
「大社高校のようにクラウドファンディングで資金を集め、支援者とのつながりを築きたい」と考えていらっしゃる方は、ぜひLEAGUEにご相談ください。LEAGUEは国内のクラウドファンディングだけではなく、海外のクラウドファンディングについても数多く携わってきました。
企画の立ち上げから実行、支援者の方々とのやりとりまで、LEAGUEでは無料でご相談を承っています。あなたの新たな挑戦を、私たちと一緒にクラウドファンディングで実現させませんか?


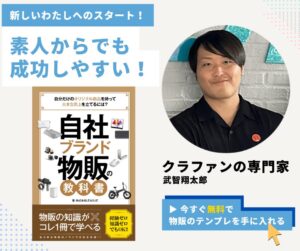
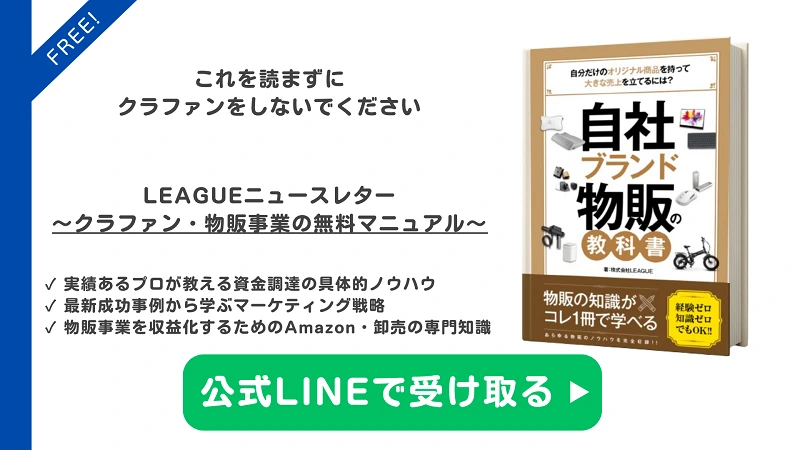





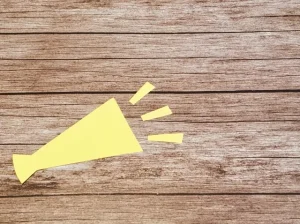




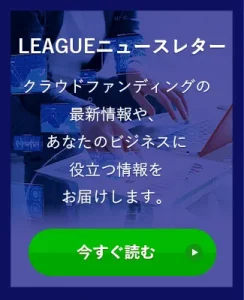
コメント